「最近、BIM/CIMってよく聞くけど、一体何のこと?」「国土交通省が推進しているのは知ってるけど、うちの会社にも関係あるの?」
建設業界にいると、こんな疑問を抱くことが増えてきたのではないでしょうか。
結論から言うと、建設業界で今後も活躍していきたいなら、国土交通省が進めるBIM/CIMは避けては通れない重要なテーマです。なぜなら、2023年度から公共事業での「原則適用」がスタートし、建設業界のスタンダードになりつつあるからです。
例えば、私の知人が所属する中堅の建設会社では、BIM/CIMへの対応が遅れたことで、得意としていた公共工事の入札で苦戦を強いられるケースが出てきたそうです。
「もっと早くから準備しておけば…」と嘆いていましたが、まさに他人事ではありません。
もちろん、「導入コストがかかるし、覚えることも多くて大変そう」「うちはまだ小規模だから関係ない」といった声があるのも事実です。確かに、新しい技術を導入するには時間もコストもかかります。
しかし、BIM/CIMは単なる3Dソフトではありません。設計から施工、維持管理までの全工程で情報を一元管理し、建設業界全体の生産性を劇的に向上させる可能性を秘めた「働き方改革の切り札」です。
長期的に見れば、コスト以上のメリットをもたらし、企業の競争力を高めることにつながります。
この記事では、国土交通省の動向を中心に、BIM/CIMの基本から実践的な対応方法、そして今後の展望まで、どこよりも分かりやすく、そして詳しく解説していきます。
BIM/CIMの基本を解説!国土交通省の定義や目的とは?

まずは「BIM/CIMってそもそも何?」という基本のキからおさらいしていきましょう。
言葉は聞いたことがあっても、正確な意味は意外と知らないものです。ここでは、国土交通省の定義や目的も交えながら、わかりやすく解説します。
BIM/CIMとは?今さら聞けない基本をわかりやすく解説
BIM/CIM(ビムシム)とは、一言でいうと「3次元モデルに関連情報をたくさん詰め込んで、建設プロセス全体で活用していく仕組み」のことです。
もう少し分解してみましょう。
- BIM(Building Information Modeling): 主に建築分野で使われる手法です。コンピューター上に建物の3Dモデルを作成し、そこ仕上げ材やコスト、管理情報といった属性情報を追加していきます。
- CIM(Construction Information Modeling/Management): 主に土木分野で使われる手法です。BIMの考え方を土木分野に応用したもので、計画、調査、設計段階から3Dモデルを導入し、その後の施工、維持管理の各段階においても情報を充実させながら活用していきます。
国土交通省は、これらをあわせて「BIM/CIM」と呼んでいます。単に3Dモデルを作って終わりではなく、そのモデルに様々な情報を紐づけて、関係者間で共有・活用することで、プロジェクト全体の効率化を図るのが最大の目的です。
BIMとCIMの具体的な違い
BIMとCIMは、どちらも3次元モデルを活用する点は同じですが、対象とする分野や目的が少し異なります。以下の表で違いを整理してみました。
| 項目 | BIM (Building Information Modeling) | CIM (Construction Information Modeling) |
| 主な対象分野 | 建築物(ビル、マンション、住宅など) | 土木構造物(道路、橋、ダム、トンネルなど) |
| 主な目的 | 設計の効率化、意匠・構造の確認、施工シミュレーション、コスト管理 | 地形・地質データの活用、施工計画の最適化、維持管理の効率化 |
| 扱うデータの特色 | 部材の属性情報、設備情報、コスト情報など | 地形データ、地質データ、測量データ、周辺環境データなど |
| 代表的なソフト | Autodesk Revit, Graphisoft Archicad など | Autodesk Civil 3D, Bentley Systemsの各種ソフトなど |
もともとは建築分野で先行していたBIMの考え方を、広範囲で画一的でない地形などを扱う土木分野に適用したのがCIM、とイメージすると分かりやすいかもしれません。
もしBIMとCADの違いについても確認したい場合は以下の記事も参考にしていただければと思います。
なぜ国土交通省はBIM/CIMを推進するのか?その目的と背景
国土交通省がここまで強力にBIM/CIMを推進するのには、日本の建設業界が抱える深刻な課題が背景にあります。
主な目的は、2016年から始まった「i-Construction(アイ・コンストラクション)」という取り組みの実現です。
これは、ICT技術を全面的に活用して建設現場の生産性を向上させ、もっと魅力的な建設現場を目指すための施策です。
具体的には、以下の3つのような目的があります。
- 生産性の向上: 3Dモデルを使うことで、設計図面の不整合や干渉箇所を事前に発見でき、現場での手戻りや作り直しを大幅に削減できます。これにより、工期短縮やコスト削減につながります。
- 品質の確保・向上: 複雑な構造物でも3Dモデルで視覚的に確認できるため、関係者間の合意形成がスムーズに進みます。完成形を正確にイメージできるので、施工ミスを防ぎ、品質の向上に貢献します。
- 働き方改革の実現: 熟練技術者のノウハウを3Dデータとして蓄積・共有することで、若手技術者への技術継承が容易になります。また、現場作業の効率化により、長時間労働の是正も期待されています。
少子高齢化による担い手不足や、インフラの老朽化といった課題を解決するための切り札として、BIM/CIMに大きな期待が寄せられているのです。
国土交通省のBIM/CIM推進委員会とは?
国土交通省のBIM/CIM推進委員会は、BIM/CIMの普及と定着を目的として設置された有識者会議です。
学識経験者、建設業界団体、コンサルタント、ゼネコン、ソフトウェアベンダーなど、各分野の専門家が集まり、BIM/CIMに関する政策や技術的な課題について議論しています。
具体的には、BIM/CIM関連のガイドラインや要領の策定、今後のロードマップの検討などを行っており、日本のBIM/CIM政策の方向性を決める重要な役割を担っています。
委員会の議事録は以下のBIM/CIMポータルサイトで公開されており、最新の動向を知る上で貴重な情報源となります。
2023年から始まった「BIM/CIM原則適用」とは?対象工事を解説
建設業界に大きなインパクトを与えたのが、2023年度からの「BIM/CIM原則適用」です。
これは、国土交通省が発注する「詳細設計を含む工事」および「詳細設計」において、原則としてBIM/CIMモデルの活用を義務付けるというものです。
「原則適用」と聞くと、「すべての公共工事でBIM/CIMが必須になったの?」と誤解しがちですが、現時点では対象が限定されています。具体的には、大規模な構造物を含む工事や、複雑な設計が求められる工事などが主な対象です。
ただし、国土交通省は今後、段階的に対象範囲を拡大していく方針を示しています。将来的には、より多くの公共事業でBIM/CIMが当たり前に使われる時代が来ることを見据えて、今から準備を進めておくことが非常に重要です。
BIM/CIM導入で得られるメリットと直面する課題
BIM/CIMの導入は、企業にとって大きな変化を伴いますが、それに見合うだけのメリットがあります。一方で、乗り越えるべき課題も存在します。
【主なメリット】
- フロントローディングによる生産性向上: プロジェクトの初期段階(フロント)に業務負荷(ローディング)をかけ、3Dモデルを作り込むことで、後工程での手戻りを防ぎ、全体の生産性を向上させます。
- 関係者間のスムーズな合意形成: 2D図面では分かりにくい部分も、3Dモデルなら誰でも直感的に理解できます。これにより、発注者や協力会社との打ち合わせがスムーズに進みます。
- 維持管理段階での活用: 竣工後もBIM/CIMモデルは活躍します。修繕履歴や点検記録などをモデルに紐づけておくことで、効率的な維持管理が可能になります。
- 安全性の向上: 重機や作業員の動きをシミュレーションすることで、危険箇所を事前に洗い出し、安全対策を立てることができます。
【直面する課題】
- 導入コスト: 高性能なパソコンや専用ソフトウェアの導入には、初期投資が必要です。
- 人材の育成: BIM/CIMを使いこなせる技術者の育成には時間がかかります。社内での研修や外部セミナーへの参加など、継続的な教育が必要です。
- データ形式の標準化: 異なるソフトウェア間でのデータ交換がスムーズにいかない場合があります。業界全体でのデータ標準化が今後の課題です。
これらの課題を理解し、計画的に導入を進めることが成功の鍵となります。
【実践編】国土交通省のBIM/CIMへの対応と今後の動向

BIM/CIMの基本がわかったところで、次は「じゃあ、具体的に何をすればいいの?」という実践的な内容に移っていきましょう。
最新のガイドラインから、スキルアップの方法、そして今後の展望まで、具体的なアクションにつながる情報をお届けします。
最新版!国土交通省のBIM/CIM関連ガイドラインと取扱要領
BIM/CIMを実務で活用する上で、必ず参照しなければならないのが、国土交通省が公開している各種ガイドラインや要領です。
これらは、BIM/CIMモデルの作成方法や納品ルールなどを定めた、いわば「公式ルールブック」です。
内容は定期的に改訂されるため、常に最新版を確認することが重要です。これらの資料は、国土交通省の「BIM/CIMポータルサイト」で一括して公開されています。ブックマークしておき、定期的にチェックする習慣をつけましょう。
このサイトには、ガイドラインだけでなく、Q&Aや活用事例なども掲載されており、BIM/CIMに関するあらゆる情報が集約されています。
国土交通省が推奨するBIM/CIM対応ソフト
BIM/CIMを始めるには、専用のソフトウェアが必要です。国土交通省が特定のソフトを「公式推奨」しているわけではありませんが、国内で広く使われている代表的なソフトはいくつかあります。
- Autodesk社: 建築向けの「Revit」や土木向けの「Civil 3D」、統合モデルを確認できる「Navisworks」などが有名です。業界標準として多くの企業で導入されています。
- Graphisoft社: 建築BIMソフト「Archicad」を提供しており、直感的な操作性が特徴です。
- Bentley Systems社: 土木分野に強く、道路や橋梁、プラント設計など、大規模インフラ向けのソリューションを多数提供しています。
どのソフトを選ぶかは、自社の事業分野や得意な工事の種類、そして取引先の状況などを考慮して総合的に判断する必要があります。無料体験版などを活用して、実際に操作性を試してみるのがおすすめです。
BIM/CIMの積算基準はどうなる?今後の検討状況をチェック
現在、建設工事の費用を算出する「積算」は、2D図面を元に行うのが一般的です。しかし、BIM/CIMが普及すれば、3Dモデルから直接、数量を算出して積算を行うことが可能になります。
これにより、積算業務の大幅な効率化が期待されていますが、まだ課題も多く、本格的な移行には至っていません。国土交通省では、BIM/CIMモデルを活用した積算要領の策定を進めており、試行工事などを通じて検討を重ねています。
将来的には、設計から積算、施工までが3Dモデルで一気通貫につながる仕組みが構築される見込みです。この分野の動向も、今後の建設業界の生産性を左右する重要なポイントとして注目しておく必要があります。
スキルアップに必須!国土交通省関連のBIM/CIM講習会情報

BIM/CIMを導入する上で最大の課題ともいえるのが「人材育成」です。これに対応するため、国土交通省や地方整備局、関連団体などが様々な講習会やセミナーを開催しています。
これらの講習会では、ソフトウェアの基本的な操作方法から、国土交通省の要領に沿ったモデル作成の実践的なトレーニングまで、幅広い内容を学ぶことができます。
- 国土交通省 地方整備局: 各地方整備局が主催する研修や説明会。
- (一社)建設コンサルタンツ協会: コンサルタント向けの研修。
- (一社)日本建設業連合会: ゼネコン向けの研修。
- ソフトウェアベンダー: 各ソフトウェアメーカーが主催するトレーニング。
自社の状況や個人のスキルレベルに合った講習会に参加することが、効率的なスキルアップへの近道です。
BIM/CIM管理技士やその他のBIM資格はどんなものがある?
BIM/CIMスキルを客観的に証明する資格も増えてきています。資格取得は、個人のキャリアアップはもちろん、企業の技術力をアピールする上でも有効です。
- BIM/CIM管理技士: 日本BIM協会が認定する資格で、BIM/CIMプロジェクト全体を管理する能力を証明します。
- BIM利用技術者試験: 一般社団法人コンピュータ教育振興協会(ACIL)が実施。BIMソフトウェアの操作スキルや知識を問います。
- 各ソフトウェアの認定資格: Autodesk社やGraphisoft社などが、自社製品に関する認定資格制度を設けています。
これらの資格取得を目標に学習を進めることで、体系的な知識とスキルを身につけることができるでしょう。


必見!国土交通省のBIM/CIMポータルサイト活用術
先ほども少し触れましたが、「国土交通省 BIM/CIMポータルサイト」は、BIM/CIMに取り組むすべての人にとっての必須ツールです。
このサイトを使いこなすことで、最新情報を効率的に収集できます。
- 基準・要領: ガイドラインや実施要領の最新版がPDFでダウンロードできます。
- マニュアル・様式: モデル作成のマニュアルや各種様式が手に入ります。
- BIM/CIM活用事例: 他の企業がどのようにBIM/CIMを活用しているのか、具体的な事例を学ぶことができます。
- 講習会・イベント情報: 全国の講習会やセミナー情報が集約されています。
- よくある質問(Q&A): 実務でつまずきやすいポイントがまとめられており、問題解決のヒントになります。
まずはこのサイトを隅々までチェックし、どのような情報があるのかを把握することから始めましょう。
【建設分野】BIM/CIMの具体的な活用事例を紹介
建築分野では、BIMの活用がかなり進んでいます。例えば、ある大規模な複合ビルの建設プロジェクトでは、設計段階でBIMを導入。
鉄骨や配管、電気設備などをすべて3Dモデルで作成し、バーチャル空間で組み合わせることで、1000箇所以上もの干渉箇所を事前に発見しました。
もし、これを発見できないまま現場で施工を進めていたら、大規模な手戻り工事が発生し、工期やコストに甚大な影響を与えていたはずです。BIMによって、こうしたリスクを未然に防ぐことができたのです。
【土木分野】BIM/CIMの具体的な活用事例を紹介
土木分野でも、CIMの活用事例が増えています。特に、山岳地帯での道路建設プロジェクトでは、ドローンで測量した広範囲の地形データを元に3Dの地形モデルを作成。
その上に道路の3Dモデルを配置することで、最適なルートや切土・盛土の量を正確にシミュレーションしました。
これにより、環境への影響を最小限に抑えつつ、経済的な設計が可能になりました。また、完成後のイメージをCG動画で作成し、地域住民への説明会で活用したところ、プロジェクトへの理解がスムーズに進んだという効果もありました。
今後のBIM/CIMはどうなる?国土交通省のロードマップを読み解く
国土交通省は、BIM/CIMのさらなる普及に向けたロードマップを示しています。
短期的には、BIM/CIM原則適用の対象工事を拡大していく方針です。中長期的には、建築分野と土木分野のデータ連携を強化し、都市全体の3Dモデル(プラットフォーム)を構築する構想もあります。
これにより、個別の建設プロジェクトだけでなく、まちづくりや防災計画、インフラの維持管理といった、より大きなスケールでBIM/CIMデータを活用していく未来が描かれています。
まさに、建設業界の枠を超えた社会全体のデジタルトランスフォーメーション(DX)につながる壮大な計画と言えるでしょう。
以下のページで「BIM/CIM取扱要領(令和7年3月)」および「BIM/CIM活用ガイドライン(案)(令和4年3月)」が確認できるのでロードマップとして活用できると思います。
まとめ:今後のBIM/CIMは国土交通省の動向を注視しよう
今回は、国土交通省が進めるBIM/CIMについて、基本から実践、そして未来までを網羅的に解説してきました。
記事のポイントまとめ
- BIM/CIMは3Dモデルに情報を詰め込む仕組み: 建築(BIM)と土木(CIM)の両方で活用され、建設プロセス全体の生産性向上を目指す。
- 国土交通省が推進する背景: i-Constructionの一環として、生産性向上、品質確保、働き方改革を実現するため。
- 2023年度から原則適用がスタート: 対象工事は限定的だが、今後は拡大される見込み。早期の対応が不可欠。
- 情報収集はポータルサイトが中心: 最新のガイドラインや事例は、国土交通省のBIM/CIMポータルサイトで必ずチェックする。
BIM/CIMは、もはや一部の先進的な企業だけのものではありません。国土交通省の本気度を見てもわかるように、これからの建設業界のスタンダードとなる技術です。
「難しそう」と敬遠するのではなく、まずは情報収集から始めてみませんか?この記事が、その第一歩を踏み出すきっかけになれば幸いです。建設業界の未来を創るこの大きな変革の波に、ぜひ一緒に乗っていきましょう。
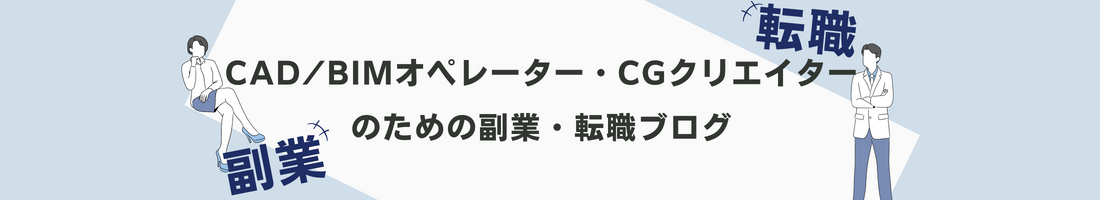




コメント