「これからの建設業界で生き残るには、どんなスキルが必要なんだろう…」
「BIM/CIMってよく聞くけど、具体的にどんな資格があって、取るとどんないいことがあるの?」
もしあなたが今、こんな風に考えているなら、この記事はきっと役に立つはずです。結論から言うと、これからの建設業界でキャリアアップを目指すなら、「BIM/CIM管理技士」の資格取得は非常に強力な武器になります。
なぜなら、国土交通省が建設業界のDX(デジタルトランスフォーメーション)を強力に推進しており、その中核技術がBIM/CIMだからです。
2025年度からは、すべての公共事業でBIM/CIMの原則適用が始まります。つまり、BIM/CIMを使いこなせる技術者の需要が、今後爆発的に高まることは間違いありません。
例えば、私の周りの現場監督も、最近はBIM/CIMの話題で持ちきりです。「次の現場、BIM/CIM対応だから勉強しないと…」「資格を持ってる若手が、どんどん重要なポジションを任されてるよ」なんて声を毎日のように聞きます。
これは、もはや一部の先進的な企業だけの話ではないんです。
もちろん、「新しい技術を学ぶのは大変そう…」「本当に資格を取るメリットがあるの?」と感じるかもしれません。確かに、新しいことを学ぶには時間も労力もかかります。
しかし、建設業界が大きな変革期を迎えている今、この波に乗るか乗らないかで、5年後、10年後のキャリアは大きく変わってくるでしょう。
BIM/CIM管理技士は、その変化の最前線で活躍するためのパスポートのようなもの。この記事を読めば、その価値と、あなたにとっての具体的なメリットがはっきりと見えてくるはずです。
さあ、一緒に未来の建設業界で活躍するための第一歩を踏み出しましょう!
BIM/CIM管理技士とは?注目される理由と取得のメリット

まずは、「BIM/CIM管理技士って、一体何をする人なの?」という基本的なところから、その将来性や取得するメリットについて、じっくりと解説していきますね。
そもそもBIM/CIMの基本を解説
BIM/CIM管理技士の話をする前に、まずは基本となる「BIM/CIM(ビムシム)」について簡単におさらいしておきましょう。
BIM(Building Information Modeling)とCIM(Construction Information Modeling/Management)は、どちらも3次元モデルをベースに、企画、調査、設計、施工、維持管理といった建設生産プロセス全体の情報を一元管理する考え方や仕組みのことです。
- BIM:主に建築分野で使われる言葉です。
- CIM:主に土木分野で使われる言葉です。
国土交通省は、このBIMとCIMを合わせて「BIM/CIM」という統一の呼称を使っています。
これまでの建設プロセスは、2次元の図面が基本でした。設計、施工、維持管理と各段階で情報が分断されがちで、手戻りや情報の伝達ミスが発生しやすいという課題があったんです。
しかし、BIM/CIMでは、3次元モデルにコストや仕上げ、部材の仕様、管理情報といった様々なデータを紐づけて一元管理します。これにより、関係者間での情報共有がスムーズになり、業務の効率化や生産性の向上、品質の確保が期待できるというわけです。
まさに、建設業界の働き方を根本から変える、革命的な技術と言えるでしょう。
ちなみにBIMとCADの違いについて知りたい方は以下の記事を参考にしていただければと思います。
BIM/CIM管理技士の役割と具体的な仕事内容
では、そんなBIM/CIMを活用する上で、「BIM/CIM管理技士」はどのような役割を担うのでしょうか。
一言でいうと、BIM/CIM管理技士は、BIM/CIMを活用したプロジェクトを円滑に進めるための専門家です。
具体的な仕事内容は多岐にわたりますが、主に以下のような業務を担当します。
- BIM/CIM導入計画の策定:プロジェクトの特性に合わせて、BIM/CIMをどのように活用するか計画を立てます。
- 3Dモデルの作成・管理:設計図書を基に3Dモデルを作成したり、各担当者が作成したモデルを統合して管理したりします。
- 情報共有のハブ役:設計者、施工者、発注者など、様々な関係者の間でBIM/CIMモデルを介した情報共有を促進します。
- 干渉チェックと調整:3Dモデル上で、部材同士の干渉(ぶつかり)などを事前にチェックし、設計の修正を促します。
- 施工シミュレーション:施工手順を3Dモデルで可視化し、安全性や効率性を検討します。
- 維持管理データの活用:完成した構造物の維持管理に必要な情報をモデルに付与し、将来の活用に備えます。
このように、BIM/CIM管理技士は、単にCADソフトを操作するオペレーターではありません。プロジェクト全体を俯瞰し、BIM/CIMというツールを使って、生産性向上や品質確保を実現する、いわば「建設プロジェクトのDX推進リーダー」のような存在なのです。
BIM/CIM管理技士は国家資格?国交省との関係について
「BIM/CIM管理技士」という名前から、「国家資格なの?」と疑問に思う方も多いかもしれませんね。
結論から言うと、BIM/CIM管理技士は、2025年8月現在、国家資格ではありません。 公益財団法人 日本建設情報技術センターが認定する民間の資格です。
しかし、「なんだ、民間資格か…」とがっかりするのは早いです。この資格が非常に注目されている背景には、国土交通省の強力な後押しがあります。
先ほども触れましたが、国土交通省は建設業界の生産性向上を目指す「i-Construction」という取り組みを推進しており、その核となるのがBIM/CIMの活用です。
そして、2025年度からは、国が発注するすべての公共事業において、原則としてBIM/CIMを活用することが義務付けられました。
これは何を意味するでしょうか?
そうです、公共事業を受注する建設会社にとって、BIM/CIMを扱える技術者の確保が必須になるということです。
BIM/CIM管理技士の資格は、国が求めるBIM/CIMの知識やスキルを持っていることを客観的に証明するものです。
そのため、民間資格でありながら、公共事業の入札などで技術力を示す指標として、今後ますます重要性が高まっていくと考えられます。
「CIMの国家資格は?」「BIMの国家資格はあるの?」という疑問を持つ方もいるかもしれませんが、現時点ではBIM/CIM分野に特化した国家資格は存在しません。
だからこそ、このBIM/CIM管理技士が、事実上の標準的なスキル証明として価値を持っているのです。
BIM利用技術者試験、BIMコーディネーター、BIMマネージャー、との違い
BIM/CIM関連の資格や役割を調べていると、「BIM利用技術者試験」や「BIMコーディネーター」、「BIMマネージャー」といった言葉も目にするかもしれません。
BIM/CIM管理技士とどう違うのか、混乱してしまいますよね。ここでそれぞれの違いを整理しておきましょう。
- BIM利用技術者試験:こちらは、一般社団法人コンピューター教育振興協会が実施している資格試験です。BIM/CIM管理技士が土木分野も含めた国の基準に準拠しているのに対し、BIM利用技術者試験は特に建築分野におけるBIMの知識と技能を問う内容が中心です。どちらもBIMのスキルを証明する資格ですが、対象とする領域や準拠する基準に違いがあります。
- BIMコーディネーター:これは資格名ではなく、プロジェクトにおける役割(ロール)を指す言葉です。BIMモデラー(3Dモデルを作成する人)と設計者・施工者などの間に立ち、モデルの調整や情報共有を円滑に進める調整役を担います。技術的な知識とコミュニケーション能力の両方が求められるポジションです。
- BIMマネージャー:BIMコーディネーターをさらに統括し、プロジェクト全体のBIM活用を管理・推進する責任者の役割です。BIM導入計画の策定から、ルールの標準化、人材育成まで、より経営的な視点が求められます。資格ではなく、豊富な実務経験と高度なマネジメント能力が必要とされる役職と言えるでしょう。
簡単にまとめると、BIM/CIM管理技士とBIM利用技術者試験は「資格」、BIMコーディネーターとBIMマネージャーは「役割・役職」という違いがあります。
まずはBIM/CIM管理技士のような資格を取得し、実務経験を積みながら、将来的にコーディネーターやマネージャーといった役割を目指していくのが一般的なキャリアパスと言えるでしょう。
BIM/CIM管理技士を取得する5つのメリット
では、具体的にBIM/CIM管理技士の資格を取得すると、あなたにとってどんないいことがあるのでしょうか。ここでは、主なメリットを5つに絞ってご紹介します。
技術者としての市場価値向上
最大のメリットは、なんといっても技術者としての市場価値が格段に上がることです。
前述の通り、2025年度からのBIM/CIM原則適用により、このスキルを持つ技術者は引く手あまたになります。しかし、現状ではBIM/CIMを使いこなせる人材はまだまだ不足しているのが実情です。
需要が高いのに、供給が少ない。これは、あなたの市場価値が上がることを意味します。
資格を持っていることで、BIM/CIMに関する知識とスキルを客観的に証明でき、社内での評価はもちろん、業界全体から見ても「貴重な人材」として認識されるようになります。
転職やキャリアアップで有利に働く
市場価値が上がれば、当然、転職やキャリアアップにおいても有利に働きます。
多くの建設会社がBIM/CIM技術者の確保に躍起になっているため、「BIM/CIM管理技士」の資格は、転職市場において非常に強力なアピールポイントになります。
- より待遇の良い会社へ転職する
- BIM/CIM部門などの専門部署へ異動する
- プロジェクトの責任者など、より上流のポジションを目指す
といった、あなたの望むキャリアパスを実現しやすくなるでしょう。特に、BIM/CIMの導入をこれから本格化させたいと考えている企業にとっては、即戦力として活躍できるあなたのような人材は喉から手が出るほど欲しいはずです。
既に転職を考えている人はまずは以下の記事で紹介しているような建設業界に強い転職エージェントに登録することをオススメします。
転職はタイミングなので資格を取ってから登録だとチャンスを逸してしまう場合もあるので。ぜひ参考にしてみてください。
公共工事の受注で有利になる可能性がある
会社にとっても、あなたがBIM/CIM管理技士であることは大きなメリットになります。
公共工事の入札では、企業の技術力を評価する「総合評価落札方式」が採用されることが多くあります。
この評価項目の中に、「BIM/CIM活用実績」や「配置予定技術者の能力」といったものが含まれるケースが増えています。資格保有者がいることは、企業のBIM/CIM対応能力が高いことの証明となり、入札で有利に働く可能性があるのです。
あなたが資格を取得することで会社に貢献できれば、当然、社内での評価や待遇にも反映されやすくなるでしょう。
資格取得にかかる費用と期間の目安は?
資格取得を目指す上で、費用と学習期間は気になるところですよね。
費用について
BIM/CIM管理技士の資格認定試験の受験料は、16,500円(税込)です。(2024年度実績)
この他に、テキスト代や、必要に応じて講習会に参加する場合はその受講料がかかります。
- 公式テキスト:約4,000円~6,000円
- 講習会・セミナー:数万円~十数万円
学習期間について
必要な学習期間は、あなたの現在の知識や経験によって大きく変わります。
- BIM/CIMの実務経験がある方:1ヶ月~3ヶ月程度
- 建設業界の知識はあるがBIM/CIMは未経験の方:3ヶ月~6ヶ月程度
- 建設業界もBIM/CIMも未経験の方:6ヶ月~1年程度
あくまで目安ですが、計画を立てる際の参考にしてください。働きながら学習を進める方がほとんどだと思いますので、無理のないスケジュールを組むことが大切です。
BIM/CIM管理技士の資格認定試験に合格するための完全ガイド
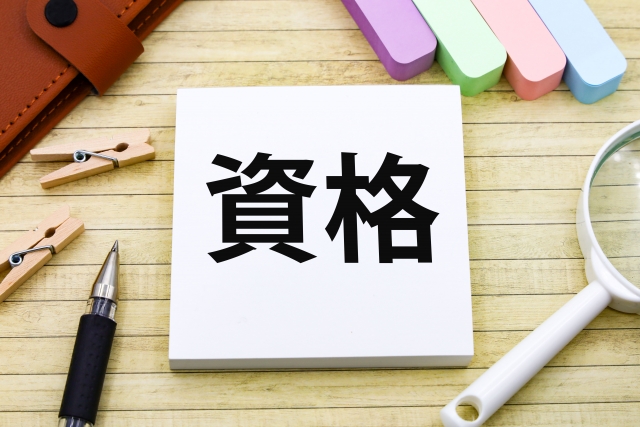
ここからは、いよいよ資格試験そのものに焦点を当てて、試験の概要から具体的な勉強方法まで、合格への道のりを徹底的にガイドしていきます!
【2025年】BIM/CIM管理技士試験の概要
まずは、試験の基本的な情報を押さえておきましょう。
※以下の情報は、過去の試験実績を基にした2025年の予測です。必ず公式サイトで最新の情報を確認してください。
| 項目 | 内容(予測) |
| 試験日 | 12月上旬の日曜日 |
| 申込期間 | 9月上旬~10月下旬 |
| 試験形式 | CBT方式(コンピュータ使用) |
| 試験時間 | 120分 |
| 出題数 | 50問 |
| 合格基準 | 正答率60%以上(30問以上) |
| 受験料 | 16,500円(税込) |
受験資格と対象者
BIM/CIM管理技士の試験には、学歴や実務経験による受験資格の制限はありません。
建設業界に関わる人であれば、誰でも受験することが可能です。
主な対象者としては、以下のような方々が想定されています。
- 建設コンサルタント、ゼネコン、設計事務所などの技術者
- 発注者(国、地方自治体など)の職員
- 建設業界への就職を目指す学生
実務経験がなくてもチャレンジできるのは、嬉しいポイントですね。
試験日程と申し込み方法
例年、試験は12月上旬の日曜日に実施されます。申し込みは9月頃から開始されることが多いです。
申し込みは、公益財団法人 日本建設情報技術センターのウェブサイトから行います。受験を考えている方は、夏頃から協会のサイトをこまめにチェックするようにしましょう。
試験の出題範囲と形式
試験は、BIM/CIMに関する幅広い知識が問われます。公式テキストである「BIM/CIM概論」によると、出題範囲は大きく以下のようになっています。
- BIM/CIM概論:BIM/CIMの歴史、目的、効果など
- BIM/CIMプロジェクト:導入計画、ワークフロー、情報共有など
- BIM/CIMモデリング:3Dモデル作成の基礎、属性情報の付与など
- BIM/CIMデータ活用:積算、施工計画、維持管理への活用など
- 関連法規・基準:国土交通省の要領・基準類など
試験形式はCBT方式で、パソコンの画面に表示される問題にマウスやキーボードで解答していきます。四肢択一問題が中心です。
気になる難易度と最新の合格率
資格試験と聞いて、まず気になるのが「難易度」ですよね。
ただ合格率については公開されておらず、合格者数のみの公開です。受験者数も非公開なので合格率も算出できない状況です。
このためか、ネットでも合格率について35%前後という情報だったり、50-70%という情報だったりと様々な状況です。
上記の合格率の情報を見ると凄く簡単な資格とはいえないのが実情です。
いずれにせよ実務経験者であっても油断せずに、基礎からしっかりと学習することが合格への鍵です。
合格に必須のテキストと過去問の活用法
試験対策の基本は、公式テキストと過去問です。
公式テキスト BimCim普及推進センターが発行している「BIM/CIM概論」は、必ず手に入れましょう。試験問題の多くは、このガイドブックの内容から出題されます。まずはこのテキストを繰り返し読み込み、全体像を把握することが重要です。
過去問
残念ながら、BIM/CIM管理技士試験の過去問は、公式には公開されていません。
ただ以下のように日本建設情報技術センターのホームページにサンプル問題がありますので少しはイメージを付けられると思います。
あとは、市販されている問題集や、講習会などで過去問をベースにした演習問題を解くことができます。テキストでインプットした知識を、問題演習を通じてアウトプットする練習を繰り返しましょう。間違えた問題は、なぜ間違えたのかを必ずテキストに戻って確認することが大切です。
おすすめの勉強方法と学習時間の目安
効率的に学習を進めるための、おすすめの勉強方法と学習時間の目安をご紹介します。
独学での学習ロードマップ
- 【ステップ1】BIM/CIM概論を読み込む(1ヶ月目)
- まずは全体をざっと通読し、試験範囲の全体像を掴みます。
- 次に、各章をじっくりと精読します。分からない用語はそのままにせず、インターネットなども活用して必ず調べるようにしましょう。
- 【ステップ2】重要語句を覚える(2ヶ月目)
- 各章の重要語句やキーワードをノートにまとめ、暗記します。特に、国土交通省が定める基準や要領に出てくる用語は頻出です。
- 【ステップ3】問題集を繰り返し解く(3ヶ月目)
- 市販の問題集や模擬試験を繰り返し解きます。最低でも3回は繰り返しましょう。
- 1回目は実力試し、2回目で間違えた箇所を完璧に理解し、3回目で満点を目指す、というイメージです。
学習時間の目安としては、合計で50~100時間程度を確保したいところです。1日1時間勉強すれば、約2~3ヶ月で合格レベルに到達できる計算になります。
効率的に学ぶための講習会やセミナー
「一人で勉強するのは不安…」「短期間で集中して学びたい」という方には、資格対策の講習会やセミナーに参加するのもおすすめです。
メリット
- 経験豊富な講師から、試験のポイントを直接教えてもらえる
- 分からないことをその場で質問できる
- 最新の試験傾向などの情報を得やすい
- 同じ目標を持つ仲間と出会える
デメリット
- 独学に比べて費用がかかる
- スケジュールを合わせる必要がある
費用はかかりますが、合格への確実性を高めたい方にとっては有効な選択肢と言えるでしょう。
以下は資格運営元である日本建設情報技術センターが開催しているBIM/CIM技術者養成講座なのでまずは受講すると良いと思います。
資格の更新は必要か?
BIM/CIM管理技士の資格には、有効期間が定められており、更新が必要です。 資格の有効期間は約4年間で、更新するための明確な条件は見つかりませんでしたが、おそらく何かしらの講習を受けるなどCPD(継続的専門能力開発)の実績が必要となるのではと思います。
まだ新しい資格でもあるので、この辺りの運用は追々整備されていくと思います。
ちなみにCPDとは、他の資格にもある運用ですが講習会への参加や技術発表など、資格取得後も継続的に学習していることを示すものです。
一度取得したら終わりではなく、常に最新の知識を学び続ける姿勢が求められる資格と言えますね。
合格発表の日程と確認方法
合格発表は、例年試験日から約1ヶ月後に行われます。
合格者の受験番号が、公益財団法人 日本建設情報技術センターのウェブサイトに掲載されます。また、合否通知書も郵送されます。
合格した場合は、その後の資格登録の手続きなども忘れずに行いましょう。
まとめ:これからの建設業界で輝くBIM/CIM管理技士を目指そう
今回は、BIM/CIM管理技士について、その概要からメリット、試験対策まで詳しく解説してきました。
最後に、この記事のポイントをもう一度おさらいしましょう。
- BIM/CIM管理技士は、建設プロジェクトのDXを推進する専門家であり、国家資格ではないが国交省の後押しで将来性が非常に高い。
- 資格を取得すると、技術者としての市場価値が向上し、転職やキャリアアップ、会社の受注に有利になるなど、多くのメリットがある。
- 試験の難易度は比較的やさしく、合格率は60%以上。公式ガイドブックと問題集でしっかり対策すれば、独学でも十分に合格可能。
- 2025年度からの公共事業でのBIM/CIM原則適用により、資格の価値は今後ますます高まっていく。
建設業界は今、100年に一度とも言われる大きな変革期を迎えています。BIM/CIMは、その変化の中心にある技術です。そして、BIM/CIM管理技士は、その変化をリードしていくための重要な資格です。
新しい技術を学ぶことは、決して楽なことではないかもしれません。しかし、この一歩を踏み出すことで、あなたは未来の建設業界で必要とされる、価値ある技術者へと成長できるはずです。この記事が、あなたの挑戦を後押しするきっかけになれば、これほど嬉しいことはありません。
さあ、あなたもBIM/CIM管理技士を目指して、新しいキャリアの扉を開いてみませんか?
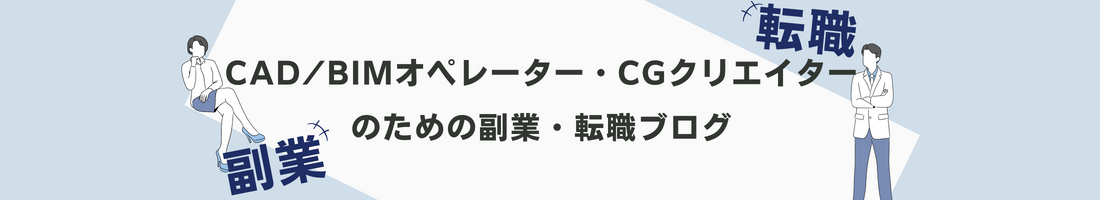





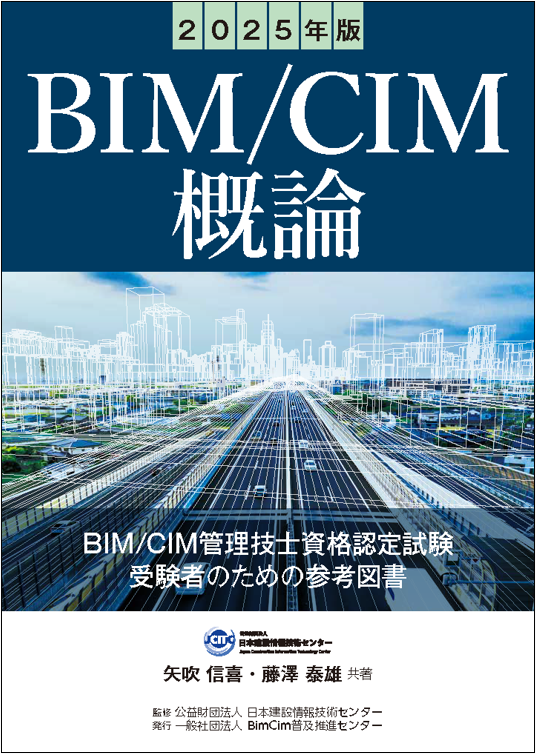




コメント