「BIMとCADって、どっちも3Dモデルを作るやつでしょ?」「今さら違いを聞けない…」
建設業界にいると、BIM(ビム)という言葉を耳にする機会が本当に増えましたよね。
でも、長年使ってきたCAD(キャド)と何が違うのか、いまいちピンとこない方も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、BIMとCADの最も大きな違いは「情報の扱い方」にあり、似ているようで別物です。
これからの建設業界でキャリアアップを目指すなら、この違いを理解しておくことが非常に重要になります。なぜなら、国土交通省がBIMの活用を強力に推進しており、BIMスキルを持つ人材の価値がどんどん高まっているからです。
実際に、私の知人のCADオペレーターは、思い切ってBIMスキルを習得したことで、設計の提案など仕事の幅が格段に広がり、結果的に年収が100万円以上アップしたそうです。
彼が特に驚いていたのは、設計変更があった際の効率の良さ。BIMなら一つのモデルを修正するだけで、関連する全ての図面や数量が自動で更新されるため、CADのように一つひとつ手作業で直す必要がない、とその便利さに感動していました。
もちろん、「まだ多くの現場ではCADが主流だし、今からBIMを学ぶのは大変そう…」と感じる気持ちもよく分かります。新しいことを学ぶには時間もコストもかかりますし、今の仕事で手一杯かもしれません。
しかし、建設業界全体のDX(デジタルトランスフォーメーション)化の流れは、もう誰にも止められません。今、BIMとCADの違いを正しく理解し、一歩を踏み出すことが、5年後、10年後のあなたのキャリアを大きく左右するはずです。
この記事を読めば、BIMとCADの具体的な違いから、あなたのキャリアプランにどちらが合っているのかが明確になりますよ。
そもそもBIMとCADの違いとは?基本から徹底比較
まずは、BIMとCADがそれぞれ何なのか、基本的な部分からおさらいしていきましょう。「そんなの知ってるよ!」という方も、新しい発見があるかもしれないので、ぜひお付き合いください。
CADとは「コンピューター支援設計」のためのツール

CADは「Computer-Aided Design」の略で、日本語に訳すと「コンピューター支援設計」となります。その名の通り、コンピューターを使って設計や製図作業を効率化するためのツールです。
かつてはドラフター(製図台)に向かって手で描いていた図面を、パソコン上で正確かつスピーディーに作成できるようになったのは、このCADのおかげ。
今や建設業界だけでなく、製造業やアパレル業界など、ものづくりの現場ではなくてはならない存在です。
主な役割は、2D(2次元)の図面(平面図、立面図、断面図など)を作成すること。近年では3Dモデルを作成できる「3DCAD」も普及していますが、基本的には「図面を描く」という目的で使われることが多いのが特徴です。
BIMとは「建物の情報を一元管理」する概念

一方、BIMは「Building Information Modeling」の略で、直訳すると「建物の情報をモデリングすること」となります。
ここで重要なのは、BIMが単なる3Dモデル作成ツールではない、という点です。BIMは、コンピューター上に現実と同じ建物を3Dモデルとして再現し、そこにコストや仕上げ、部材の仕様といった様々な「属性情報」を追加して、建物のデータベースを構築する考え方(概念)そのものを指します。
BIMソフトを使って作成される3Dモデルは、単なる形状データではありません。例えば、モデル上にある「壁」は、それがどんな素材で、厚さが何ミリで、耐火性能はどのくらいか、といった情報を持っています。
この情報が詰まったモデルを一つ作ることで、各種図面はもちろん、パース、数量表、見積もりなどを自動で作成したり、設計の初期段階でシミュレーションを行ったりと、建物のライフサイクル全体を通して情報を活用できるのがBIMの最大の特徴です。
【結論】BIMとCADの最も大きな違いは「情報の扱い方」
結局のところ、BIMとCADの最も大きな違いは、情報をどのように扱うかという点に集約されます。
| 項目 | CAD | BIM |
| データの単位 | 線、円、文字などの「幾何学情報」 | 壁、柱、窓などの「オブジェクト(属性情報を持つモノ)」 |
| 情報の連携 | 図面ごとに独立しており、連携は限定的 | 全てのデータが一つのモデルに紐づき、一元管理される |
| 修正時の対応 | 関連する全ての図面を手動で修正する必要がある | 一箇所修正すれば、関連する全ての図面・情報が自動で更新される |
| 主な活用フェーズ | 設計・施工段階(作図がメイン) | 企画・設計・施工・維持管理まで、建物のライフサイクル全体 |
もう少し具体的に見ていきましょう。
線をデータとして扱うCAD
CADデータは、突き詰めると「線」や「円」「文字」といった、意味を持たないただの図形の集まりです。例えば、CADで壁を描くときは、2本の平行線を引いて表現します。コンピューターはそれを「2本の線」としか認識しておらず、それが「壁」であるとは理解していません。
そのため、壁の仕様を変更したい場合は、平面図、断面図、展開図など、その壁が描かれている全ての図面を一つひとつ手作業で修正する必要があります。
部材をデータとして扱うBIM
一方、BIMでは「壁ツール」を使って壁を作成します。このとき作られるのは単なる線ではなく、「厚さ300mmのコンクリート壁」といった属性情報を持った「壁オブジェクト」です。
コンピューターはこれを「壁」として認識しているため、この壁オブジェクトの厚さを250mmに変更すれば、平面図、断面図、3Dモデル、さらには数量表に至るまで、関連する全てのデータが自動的に更新されます。この整合性を保つ仕組みが、BIMの強力な武器となっています。
3DCADとBIMの違いは「属性情報」の有無
「じゃあ、3Dモデルが作れる3DCADとBIMは何が違うの?」という疑問もよく聞かれます。
見た目はどちらも立体的なモデルなので、混同しやすいですよね。しかし、この二つにも決定的な違いがあります。それが、先ほどから何度も出てきている**「属性情報」を持つかどうか**です。
3DCADは、あくまでも2DCADの延長線上にあり、3D空間に線や面を組み合わせて「形状」を作るためのツールです。モデルは単なる「ハリボテ」のようなもので、そこに建材の仕様やコストといった情報は含まれていません。
対してBIMは、形状データに加えて、部材の仕様、メーカー、価格、メンテナンス履歴といった、建物のデータベースとなる属性情報を持っています。見た目は同じ3Dモデルでも、その中身の情報量が全く異なるのです。
ちなみに自動車業界にもBIMに似たツールがあります。それは3DAや3D図面と呼ばれることがありますが、基本的にはBIMと同じ目的で単なる3Dモデルでなく、そこに幾何公差などの製造上の属性情報を持たせることでシミュレーションや後工程の自動化に寄与しています。
目的と活用フェーズの違い
情報の扱い方が違うということは、当然、その目的や使われる場面も変わってきます。
CADの目的は「2D図面の作成」
CADの主な目的は、設計情報を伝えるための「2D図面」を、いかに効率よく正確に作成するかという点にあります。設計から施工へと進むための、コミュニケーションツールとしての役割が強いと言えるでしょう。
BIMの目的は「企画から維持管理まで見据えた情報活用」
BIMの目的は、作図の効率化だけにとどまりません。企画・設計段階ではデザインの検討や各種シミュレーションを行い、施工段階では干渉チェックや施工手順の可視化、そして完成後は維持管理・メンテナンスのデータベースとして活用するなど、建物のライフサイクル全体を通して生産性を向上させることが大きな目的です。
土木分野で活用されるCIMとの違い
最近では、BIMと合わせて「CIM(シム)」という言葉も聞くようになりました。CIMは「Construction Information Modeling/Management」の略で、BIMの概念を橋やダム、トンネルといった土木構造物に応用したものです。
建築分野がBIM、土木分野がCIM、と覚えておくと分かりやすいでしょう。基本的な考え方は同じですが、扱う対象が違うため、地形データとの連携などがより重要視されるのが特徴です。
BIMとCADのメリット・デメリットを比較
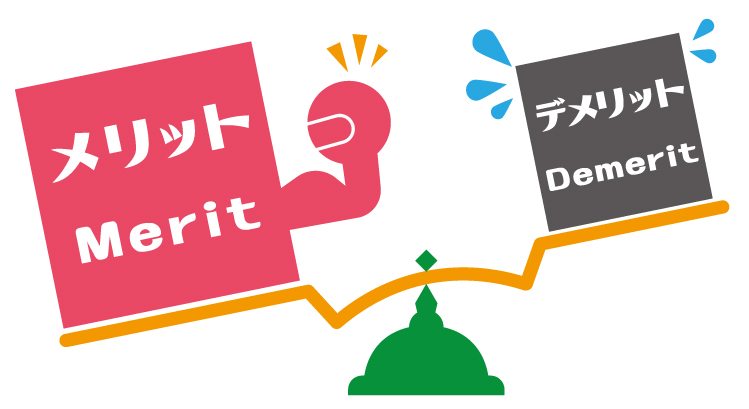
ここで、BIMとCADのメリット・デメリットを一度整理しておきましょう。
CADのメリット・デメリット
| メリット | デメリット |
| ・操作が比較的簡単で、習得しやすい | ・図面間の整合性を手動で確認する必要がある |
| ・導入コストがBIMに比べて安い | ・設計変更に手間と時間がかかる |
| ・2D図面の作成に特化しており、動作が軽い | ・数量拾いや見積もり作業が別途必要 |
| ・広く普及しており、データのやり取りが容易 | ・情報の活用が設計・施工段階に限られる |
BIMのメリット・デメリット
| メリット | デメリット |
| ・設計変更に強く、手戻りを削減できる | ・ソフトの操作習得が難しい |
| ・図面間の整合性が自動で保たれる | ・導入コスト(ソフト、PC)が高い |
| ・数量や面積などを自動で算出できる | ・プロジェクトの初期段階での入力作業が多い |
| ・建物のライフサイクル全体で情報を活用できる | ・関係者全員のBIMへの理解が必要 |
BIMとCADの違いで変わる働き方と将来性

さて、BIMとCADの技術的な違いが見えてきたところで、次に気になるのは「それによって私たちの働き方や将来性がどう変わるのか」ですよね。オペレーターの仕事内容や求められるスキル、そして将来性について見ていきましょう。
BIMオペレーターとCADオペレーターの仕事内容の違い
CADオペレーターの主な仕事は、設計者やデザイナーからの指示に基づき、CADソフトを使って図面を正確に作成・修正することです。いわば「作図のプロフェッショナル」。正確さとスピードが求められる、職人的な側面が強い仕事です。
一方、BIMオペレーターの仕事は、単に3Dモデルを作成するだけではありません。モデルに属性情報を入力したり、異なる分野(意匠、構造、設備)のモデルを統合して干渉チェックを行ったり、BIMモデルから各種資料を作成したりと、その業務は多岐にわたります。
設計者の意図を汲み取り、モデルに情報を落とし込んでいく必要があるため、より設計に近い立場での作業が多くなります。関係者とのコミュニケーションや調整役を担う場面も増えるでしょう。
求められるスキルの違い
仕事内容が違うため、求められるスキルも異なります。
CADオペレーターに求められるのは、第一にCADソフトを使いこなす高い作図スキルです。加えて、図面を正確に読み解く力や、集中力、コツコツと作業を進める忍耐力も重要になります。
BIMオペレーターには、BIMソフトの操作スキルはもちろんのこと、それ以上に建築に関する幅広い知識(意匠、構造、設備、施工など)が不可欠です。なぜなら、情報の詰まった建物モデルを作るには、その建物がどのように成り立っているかを理解している必要があるからです。また、プロジェクト全体を見渡して情報を管理する能力や、関係者と円滑に連携するためのコミュニケーション能力も求められます。
国土交通省も推進するBIMの将来性
BIMの将来性を語る上で欠かせないのが、国の後押しです。国土交通省は、建設業界の生産性向上を目指す「i-Construction」の中核としてBIM/CIMの活用を掲げており、2023年度からは公共事業において原則BIM/CIMを適用する方針を打ち出しました。
これは、国が「これからの公共事業はBIM/CIMで行います」と宣言したに等しく、今後は民間工事にもこの流れが加速していくことは間違いありません。
つまり、BIMスキルは一部の先進的な企業だけのものではなく、建設業界で働く上での「標準スキル」になりつつあるのです。需要が高まる一方で、BIMを使いこなせる人材はまだ不足しているため、BIMスキルを持つ人材の市場価値は今後ますます高まっていくでしょう。
これから学ぶならどっちがおすすめ?
「結局、これから学ぶならどっちがいいの?」
結論から言えば、将来性やキャリアアップを考えるなら、断然BIMを学ぶことをおすすめします。
もちろん、CADの需要がすぐになくなるわけではありません。今でも多くの企業でCADは現役ですし、CADオペレーターの求人もたくさんあります。一つのことを極めたい、コツコツと正確な作業をするのが好き、という方にとっては、CADオペレーターも魅力的な仕事です。
しかし、より上流工程に関わりたい、仕事の幅を広げて収入をアップさせたい、という思いがあるなら、BIMスキルを身につけることが大きなアドバンテージになります。CADの知識がある方なら、BIMの習得もスムーズに進められるはずです。
BIMの学び方
BIMに興味が出てきた方のために、具体的な学び方を2つご紹介します。
独学で学ぶ
今は書籍やYouTube、オンライン教材などが充実しているため、独学でもある程度のスキルを身につけることが可能です。自分のペースで、費用を抑えながら学べるのが最大のメリット。ただし、モチベーションの維持が難しかったり、分からないことを質問できずに挫折してしまったりする可能性もあります。
独学での学習方法については、こちらの記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
スクールやオンラインスクールで学ぶ
費用はかかりますが、プロの講師から体系的に学べるのがスクールのメリットです。分からないことをすぐに質問できる環境は、挫折を防ぐ上で非常に心強いでしょう。同じ目標を持つ仲間と出会えることも、モチベーション維持につながります。最近はオンラインで完結するスクールも増えているので、働きながらでも学びやすくなっています。
BIMが学べるスクール選びに迷ったら、こちらの記事が役立つはずです。
代表的なBIM・CADソフト一覧
世の中には様々なBIM・CADソフトがあります。代表的なものをいくつかご紹介します。
- AutoCAD(オートキャド): CADソフトの代名詞的存在。圧倒的なシェアを誇り、汎用性が高い。
- Revit(レビット): AutoCADと同じAutodesk社が開発するBIMソフト。建築設計から施工まで幅広く対応。
- ArchiCAD(アーキキャド): BIMの概念をいち早く提唱したソフト。直感的な操作性とデザイン性の高さが特徴。
- Vectorworks(ベクターワークス): 2D/3D/BIMに対応したCADソフト。建築だけでなく、インテリアや舞台照明など幅広い分野で使われる。
- SketchUp(スケッチアップ): 直感的に3Dモデルが作成できるソフト。BIMソフトではありませんが、企画段階のデザイン検討などで広く利用されています。
無料で使えるBIM・CADソフト
いきなり高価なソフトを買うのはハードルが高い、という方は、無料で使えるソフトから試してみるのも良いでしょう。
- Autodeskの学生版: 学生や教員であれば、RevitやAutoCADなどの主要ソフトを無料で利用できます。
- 各ソフトの体験版: 多くのソフトには、30日間などの期間限定で全機能を使える体験版が用意されています。
- FreeCAD: オープンソースで開発されている無料の3DCADソフト。BIM機能も搭載されています。
まとめ:BIMとCADの違いを理解してキャリアに活かそう
今回は、BIMとCADの違いについて、基本から働き方、将来性まで詳しく解説してきました。
【記事のポイント再確認】
- BIMとCADの最大の違いは、情報を「オブジェクト」で扱うか「線」で扱うか
- BIMは企画から維持管理まで、CADは主に作図フェーズで活用される
- BIMオペレーターはCADオペレーターより高い建築知識と専門性が求められる
- 将来性やキャリアアップを考えるなら、断然BIMスキルの習得がおすすめ
BIMとCADは、どちらが優れているというものではなく、それぞれに目的と役割があります。しかし、建設業界が大きな変革期を迎えている今、BIMという新しい概念を理解し、そのスキルを身につけることが、これからの時代を生き抜くための強力な武器になることは間違いありません。
この記事が、あなたのキャリアについて考えるきっかけになれば嬉しいです。まずは無料のソフトに触れてみるなど、小さな一歩から始めてみてはいかがでしょうか。
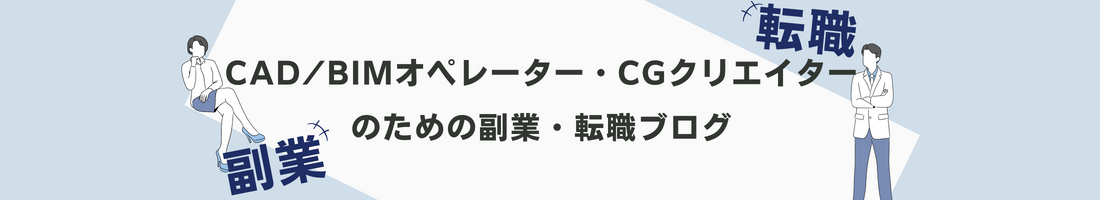

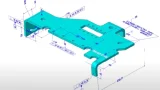




コメント