「BIMオペレーターはやめとけって聞くけど、本当なのかな…」 「将来性がない仕事なら、目指すのはやめておこうかな…」
BIMオペレーターという仕事に興味を持ち、いざ調べてみると「やめとけ」というネガティブな言葉を目にして、不安になっていませんか?
結論から言うと、BIMオペレーターは将来性が非常に高く、今だからこそ目指すべき魅力的な仕事です。
なぜなら、建設業界全体でBIMの導入が国を挙げて推進されており、BIMを扱える人材の需要が急速に高まっているからです。実際に、国土交通省はBIMの活用を原則化する方針を打ち出しており、今後BIMオペレーターの活躍の場はますます広がっていくでしょう。
例えば、私の知人にも未経験からBIMオペレーターに転職した人がいます。彼は最初、覚えることの多さや給与面で苦労した時期もあったようです。
しかし、スキルを磨き続け、今ではBIMコンサルタントとして独立し、会社員時代の何倍もの収入を得ています。彼は「あの時『やめとけ』という言葉を信じて諦めなくて本当に良かった」と話していました。
もちろん、「仕事内容の割に給料が低い」「常に勉強が必要で大変」といった声があるのも事実です。確かに、BIMオペレーターは専門的なスキルが求められるため、楽な仕事ではありません。
しかし、それはどの専門職にも言えること。そして、BIMオペレーターに関しては、正しい知識を身につけ、将来を見据えたキャリアプランを描くことで、そうしたネガティブな側面を十分に乗り越えることができます。
この記事を読めば、「BIMオペレーターはやめとけ」という言葉の裏にある真実と、あなたがこの先どうすべきかが明確になるはずです。
BIMオペレーターはやめとけと言われる理由

まず、なぜ「BIMオペレーターはやめとけ」と言われてしまうのか、その理由を一つひとつ見ていきましょう。ネガティブな意見の裏側にある実態を知ることで、BIMオペレーターという仕事への理解が深まります。
給料が仕事内容に見合っていない?年収の実態
「専門的なスキルが必要なのに、給料が安い」という声は確かによく聞かれます。BIMオペレーターの年収は、一般的に350万円〜600万円程度が相場と言われています。
経験やスキル、勤務する企業の規模によって差があり、特に経験の浅い若手のうちは、覚えることの多さや業務の専門性の高さに対して「給料が見合っていない」と感じてしまうことがあるかもしれません。
しかし、これはあくまでスタート段階の話です。BIMスキルは専門性が高く、経験を積むことで市場価値は着実に上がっていきます。特に、複数のBIMソフトを扱えたり、マネジメント経験があったりすると、年収600万円以上、さらには1000万円近くを目指すことも不可能ではありません。
給与が仕事内容に見合っていないと感じる期間は、将来への投資期間と捉える視点も大切です。
専門性が高いのに評価されにくい現実
BIMはまだ発展途上の技術であり、特に中小企業ではBIMの価値を正しく理解し、評価できる上司や経営者が少ないという現実があります。
従来の2D-CADと同じような「ただの作図担当」として扱われ、高度なBIMモデルを作成しても、その専門性や業務の複雑さが評価に結びつかないケースがあるのです。
このような環境では、モチベーションの維持が難しく、「こんなに頑張っているのに誰も評価してくれない」と感じてしまうのも無理はありません。
会社選びの際には、BIM推進にどれだけ力を入れているか、BIM技術者の評価制度が整っているかを見極めることが非常に重要になります。
常に新しいソフトの習得が必要でついていけない
BIM関連のソフトウェアは日進月歩で進化しており、次々と新しいバージョンや新しいツールが登場します。
代表的なソフトであるRevitやArchiCADなども定期的にアップデートされ、その都度新しい機能や操作方法を学ばなければなりません。
この変化の速さについていくのが大変で、「勉強し続けることに疲れた」と感じてしまう人もいます。特に、日々の業務に追われながら新しい技術を学ぶ時間を確保するのは簡単ではありません。
しかし、見方を変えれば、常に新しい知識やスキルを吸収できる刺激的な環境とも言えます。学習意欲が高い人にとっては、むしろ楽しみながら成長できる仕事でしょう。
もしBIMとCADの違いが分からない場合は以下の記事も参考にしていただければと思います。
未経験からの就職はきつい?覚えることの多さ
未経験からBIMオペレーターを目指す場合、覚えることの多さに圧倒されて「きつい」と感じることがあります。
建築の基礎知識はもちろん、BIMソフトの複雑な操作方法、各社の設計ルールなど、習得すべきことは山積みです。
入社後、十分な研修がないまま実務に入り、専門用語が飛び交う環境で孤立してしまうケースも少なくありません。
未経験からの挑戦は決して簡単な道ではありませんが、スクールに通ったり、独学で基礎を固めたりと、事前の準備をしっかり行うことで、スムーズにキャリアをスタートさせることができます。
修正指示が多くて精神的に疲弊する
BIMモデルは、設計者や施工管理者など、多くの関係者からのフィードバックを元に作り上げていきます。そのため、「もっとこうしてほしい」「ここを修正してほしい」といった指示が頻繁に発生します。
時には、度重なる修正や、関係者間の意見の食い違いによる手戻りで、精神的に疲弊してしまうこともあるでしょう。
特に、設計の初期段階では仕様変更が多く、何度もモデルを作り直すことも珍しくありません。こうした状況を乗り越えるには、粘り強さや、関係者と円滑にコミュニケーションを取りながら意図を正確に汲み取る能力が求められます。
残業が多くてプライベートとの両立が難しい
建設業界全体に言えることですが、BIMオペレーターも納期前は業務が集中し、残業が多くなる傾向があります。特に、プロジェクトの締め切りが迫ってくると、連日深夜まで作業が続くことも。
プライベートの時間を大切にしたい人にとっては、「ワークライフバランスが取りにくい」と感じる大きな要因になるでしょう。
ただし、近年では建設業界でも働き方改革が進んでおり、BIMの活用による業務効率化で残業を減らそうという動きも活発になっています。会社によっては、残業がほとんどないというケースもありますので、企業選びが重要です。
求人は多いけど条件の良い会社が少ない
BIMオペレーターの求人数は年々増加しており、仕事を見つけること自体はそれほど難しくありません。
しかし、その中身をよく見てみると、「給与が低い」「残業が多い」「研修制度が整っていない」といった、条件が良いとは言えない求人が多いのも事実です。
特に、BIM導入の初期段階にある企業では、BIMオペレーターを安価な労働力としてしか見ていないケースも見受けられます。焦って条件の悪い会社に就職してしまうと、「こんなはずじゃなかった」と後悔することになりかねません。
豊富な求人の中から、自分の希望に合った優良企業を見つけ出す情報収集能力と見極める目が必要になります。
現役BIMオペレーターの実体験
ここからは実際の現役BIMオペレーターである3名の方々に辛かった経験なども聞いてみたいと思います。
大手ハウスメーカーBIM設計者(32歳)の経験談
大手のハウスメーカーで正社員として設計の仕事をしている男性(32歳)です。
建築士の免許を持っていますが、最近は、設計にCADやBIMのスキルは必要不可欠になりました。
私の仕事は、戸建て住宅を建てる際に、施工主との打ち合わせに立ち合いヒアリングをして、施工主が望む家を設計することです。
BIMを使用して3Dモデルを作成し施工主にわかりやすくデザインを提供しています。
BIMソフトはグラフィソフト社のArchicadを使用しています。
BIMソフトの操作方法を覚えるのが大変
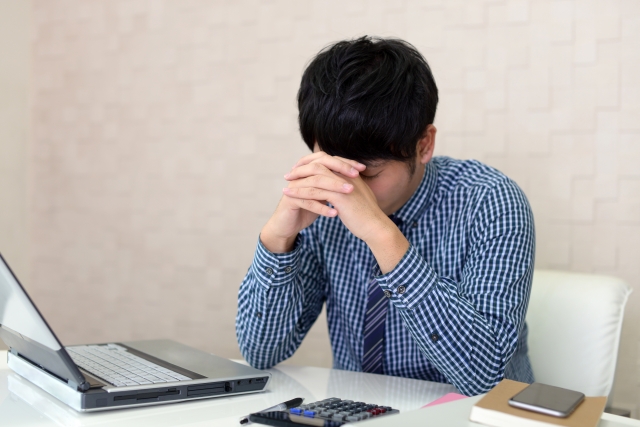
今はすっかりと慣れましたが、入社直後はBIMソフトの操作方法を覚えるのがとても大変でした。
最初は、ラインを描画するなど、基本的なところからわからなかったのでとても苦労しました。
また、BIMへの移行期は2次元図面を3D化する必要があったのですが、図面と3Dモデルのつじつまが合わず、思い通りにならないところが一番苦労しました。
一連の作業を繰り返し経験することで、最終的な3Dデータをイメージしながら設計できるようになりだんだんとなれていきました。
対処方法は、とにかくBIMソフトを使い倒し、慣れるしかないのですが、今は大学や専門学校でもBIMソフトの授業があると思うので、それをしっかりと受けることが重要だと思います。
肩こり、目の疲れ、倦怠感が辛い

私は右利きなので右手で細かいマウス操作をするため、右肩が異常に凝るところが辛いです。
時々、もうこれ以上作業できないと思えるほど痛いこともあります。
そして、長い間パソコンの前にいるため、目が疲れるとともに体がだるくなることもあります。
- 30分~1時間に一度ストレッチをする(タイマーをかけておくと良い)
- 定期的に遠くを見る
- 長時間作業用の40%以上ブルーライトカットの眼鏡にする
- パソコンにブルーライトカットフィルムを付ける
もうこればかりは現代病といっても過言ではないでしょう。
VDT(Visual Display Terminals)作業に対する影響を軽減できるように上手く付き合っていくしかないのです。
マシントラブルでデータ消失
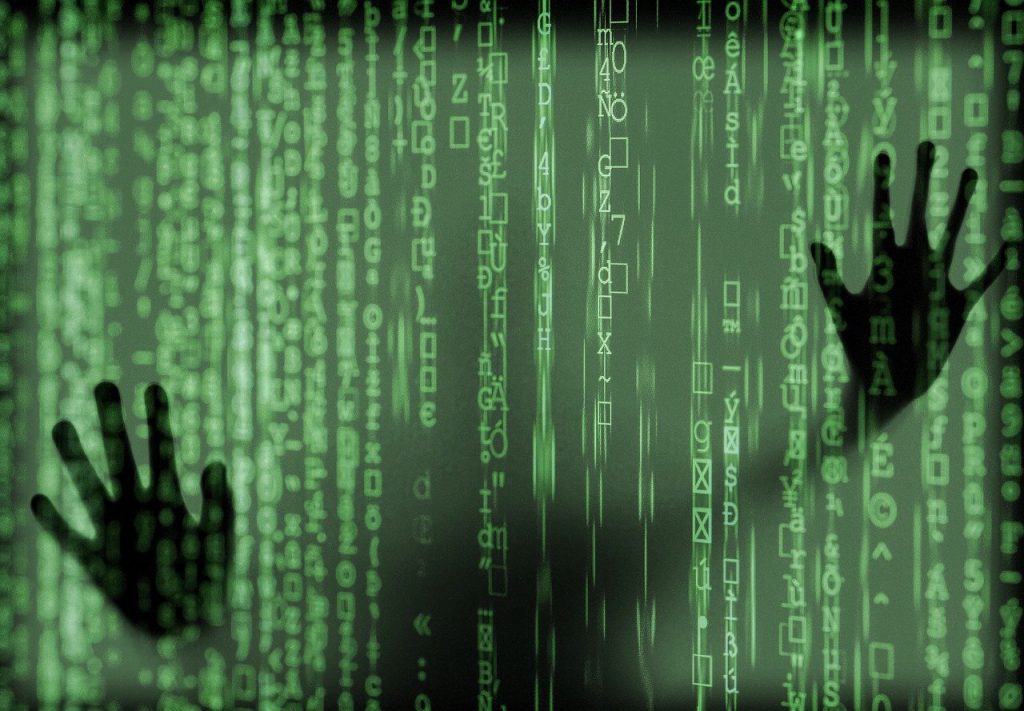
最もイライラすることはマシントラブルが時々あることです。
データが重くなりソフトのレスポンスが遅くなることも耐えられませんが、稀にソフト自体がシステムダウンしてしまい、せっかく設計したデータを失ってしまうこともあります。
基本的にBIMデータはクラウドサーバーで一元管理していいますが、データの保管はリアルタイムではなく、突然システムがダウンすると、最悪1時間前のデータしか保管されておらず、1時間分の作業が無駄になることがあります。
マシントラブルについては、システムのOSを常に最新にすることと、ローカルのマシンに設計データを置かないようにして、ローカルマシンのHDDの空き容量を常に大きくするようにしています。
また、いつマシントラブルに遭遇するかわからないため、こまめなデータのバックアップもしています。
もちろん、BIMソフトの更新状況もこまめに確認して常に最新バージョンを使うようにしています。
施工主の要望がころころ変わる
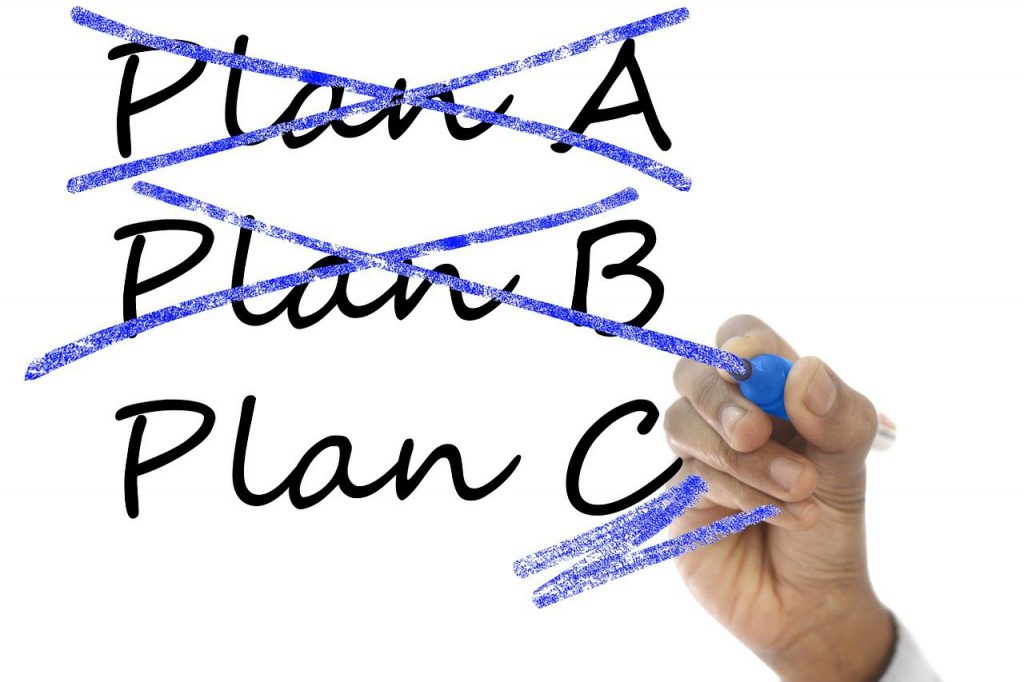
施工主に3Dモデルを見せると、要望と異なると言われることがあります。
施工主と3Dモデルを定期的に共有することで要望のずれをなくすことが極力できますが、施工主によっては、忙しくてマメに会えない人もいます。
また、インターネット環境を持っていない人もいますので、メールなどでのデータ共有が不可能なこともあります。
そのため、せっかく作ったデータを、たとえば1週間後などに施工主様からNGを言われると、設計のやり直しになってしまい、精神的にもダメージを受けるのです。
施工主とのやり取りについては、最初の打ち合わせの時に、その場でイラストを描くなどしてこまめに要望を確認するようにしています。
実際に画にして説明すると意見の食い違いも発生しにくくなりました。
将来的には、クラウド上に3Dデータをアップし、そのデータを施工主がスマホにインストールされたビューワなどを使ってデータ確認できるようにしたいと思っています。
フリーランスとしてBIMを使った設計業務(50歳)
フリーランスとしてRevitを活用したBIM設計を行っている男性(50歳)です。
住宅やオフィス等の案件で、3Dによる設計・プレゼンツール(物件紹介や住民設計)としてのBIM活用が中心です。
たまに設備設計や構造解析を行ったりします。
尺モジュール(伝統的な 910mm×910mm[半間×半間]を基準とした設計手法)で、BIMモデリングできる作業環境が整ってからは、Revitが設計・デザインの軸となり、そこから、AutoCAD や Illustrator にデータを引き継ぎ、最終納品物としての仕上げを行っています。
従来は、平面図→立面図→パースという流れで設計を進めることが多かったのですが、BIMが導入されてからは、3次元で、まず建物をモデリングし、色々な角度から検証し納得してから、図面として平面図や立面図を作図するため、設計業務の出戻りは少なくなりました。
BIMの自己学習環境が整っていない
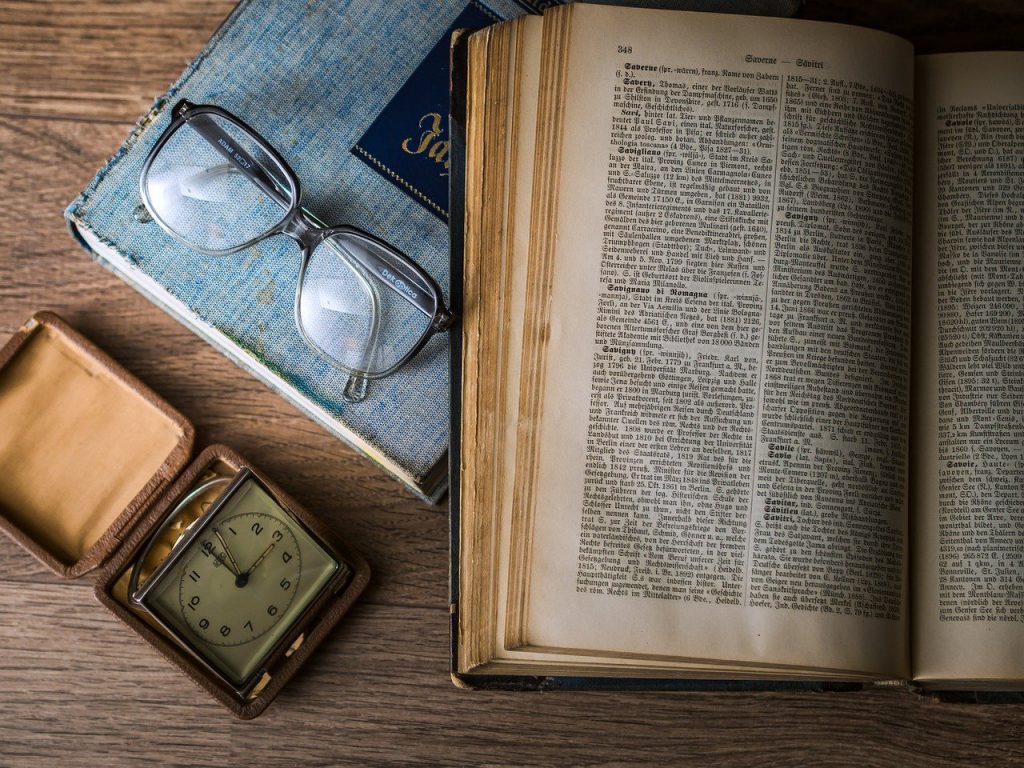
BIMオペは、まだ自己学習教材が少なく、CADスクールのようなスキルアップの場も少ないのが現状です。
動画サイトも含めて、色々なネット情報から有益な情報は得られるようにはなりましたが、断片的な情報や、ご自身の備忘録、自己表現など、体系的に実務のノウハウを取りまとめたものは、残念ながら少ないのではないでしょうか?
かつてのCAD教材・CAD教育環境の普及の歴史を振り返っても、AutoCADで実務に携わっている人の有益なノウハウが文献で公開されたのは、ようやく令和に入ってからのことと思います。
早い時期から、Autodesk社のオフィシャルマニュアルが出版され、改訂を重ねてこられたのですが、3Dモデリングに関しては、オフィシャルマニュアルを丸暗記しても、現場では不十分なのが実情でした。
したがって、現時点のBIMオペのスキルアップ手段としては、日々の情報収集、トライ&エラーの繰り返ししかないと思っています。
各人の日々の意識の向上や、自己研鑽によらざるを得ないと思います。
以下の記事にBIMの独学方法、おすすめ資格、スクールなどもまとめてありますので参考にしていただければと思います。
海外からの情報収集のため英語スキルが必要

積極的にスキルアップしようと思うと、日本国内の情報だけでは不十分で海外のサイトやフォーラムで情報収集しなければなりません。
したがって、それほど高いスキルレベルはなくとも、簡単な英語の読解力がマスト条件として要求される場面があります。
今は手書き図面からCAD図面への移行し始めた時代と同じような途上の段階にあり、現在のBIMオペは、将来の草分けとしての役割を担うことも求められていると感じています。
中小企業ではまだBIMが普及されていない
BIMという概念がスーパーゼネコンや大手設計事務所のみが取り扱う、敷居が高いツールのように思われていることで、中小・零細企業には、あまり普及していない現状があります。
これによりBIMオペのスキルがCADオペほどには評価されずらいというのが実感です。
今はCADからBIMへの過渡期なので、まだまだCADオペが重宝されやすいのかもしれませんが、これは時間が解決すると思っています。
日本政府が23年(コロナにより2年前倒し)までに完全BIM化を目標に掲げていますので、今後はBIMオペの求人が激増すると予想しています。
ゼネコンがBIMデータ提出を取引条件にした際、淘汰される中小企業は問題なので、今のうちから準備をする必要があるのです。
現に、求人を見てみても採用したあかつきにはBIMも教えますというふれこみで求人している案件を多く見ます。
BIMオペレーター正社員(36歳)
建築業界で正社員としてBIMオペレーターをしている男性(36歳)です。
納期に間に合うように、建築物の図面を作成して、上司に提出し、修正点を指摘され、修正作業して、また上司に見てもらうといったことの繰り返しです。
上司に承認されると作成した図面が現場に行くのですが、また次の現場の建築物の図面を作成するといった感じです。
使用しているBIMソフトは「アーキキャド」です。
細かい作業を続ける高い集中力が必要

BIMオペレーター特有の辛い作業としては、建築物の設計に携わることが多いので、長時間連続して同じ作業になり、精神的にまいってくることもよくあります。
形を決めながらの作業であれば単調作業ではないのですが、コストなど属性情報の入力は情報の転記になることが多く、単調作業と言わざるを得ません。
できるだけ単調作業を長時間やらないように、考える作業とのバランスを取りながら、気分をリフレッシュしながらやるようにしています。
質問などコミュニケーション能力必要
モデル作成時に分からないことが出てきた場合にはすぐに責任者や設計士に質問をしなくてはいけません。
責任者も設計者も忙しい場合が多いので、質問するタイミングを逸すると、納期に間に合わなくなってしまいます。
そこで分からないところを相手に伝わりやすく事前準備し、画面を見ながら、一回のコミュニケーションで疑問が解決するようにします。
したがって、コミュニケーション能力がある程度ないと辛い部分があります。
パソコン画面による目の疲れ、腱鞘炎、腰の痛み
BIMオペレーターの仕事について辛いことは、「1日中ずっとパソコンとにらめっこしている」ことです。
朝パソコンの前に座って、パソコン画面とにらめっこしていると、気が付けば昼になっていたり、終業時間になっていたりすることがよくあります。
細かい作業が多いと、仕事が終わった時には、目も神経も疲れ切っています。
目は慢性化してドライアイになっていますし、手もマウスをずっと握っているため、手首を痛めて腱鞘炎になっています。
長時間座りっぱなしなので腰も痛く、椅子から立ち上がるのも時間をかけて立ち上がらないと痛くて立てないということもしばしばあります。
BIMオペレーターは、気を付けていないと、身体が悲鳴を上げてしまう仕事だと思っています。
対処方法としては、集中しすぎず、アラームなどを1時間ごとにかけて、パソコンの前から離れて、ぶらぶらと廊下を歩いたり、ラジオ体操をしたりしています。
それだけでも、目が休まり、身体もスッキリするので、もう一度集中して仕事に取り組むことができます。
とにかく集中し過ぎないことがBIMオペレーターには大事だと感じています。
あとは、仕事以外の時は「しっかりと休む」ことが大事です。
家に仕事を持ち帰ってやるなんてことをしたら、後々身体に負担がかかってくるので、自分はしないようにしています。
仕事帰りにジムに行って汗をかき、リフレッシュしたりもしています。
それでもBIMオペレーターはやめとけとは言えない!将来性と向いている人

ここまで「やめとけ」と言われる理由を見てきましたが、それらはBIMオペレーターという仕事の一側面に過ぎません。
ここからは、それでもBIMオペレーターをおすすめする理由、その将来性についてお話しします。
BIM技術の将来性は高く需要は増え続ける
BIMオペレーターの最大の魅力は、その圧倒的な将来性です。現在、建設業界では深刻な人手不足と高齢化が進んでおり、生産性の向上が急務となっています。
その解決策の切り札として期待されているのが、BIMなのです。
BIMは、単なる3Dモデル作成ツールではありません。設計から施工、維持管理に至るまで、建物のライフサイクル全体の情報を一元管理し、関係者間で共有することで、業務の大幅な効率化や品質向上を実現します。
このBIMの重要性に国も注目しており、国土交通省は2023年度から直轄事業においてBIM/CIMを原則適用するなど、その活用を強力に推進しています。
国が主導してBIM化を進めているということは、今後、民間企業にもその流れが確実に波及していくことを意味します。つまり、BIMを扱える人材の需要は、今後ますます高まり、その価値も上昇していくことは間違いありません。
今はまだ過渡期だからこそ存在する問題も、BIMが普及するにつれて解決され、BIMオペレーターの待遇や働く環境はさらに改善されていくでしょう。
BIMオペの将来性や仕事内容の詳細、年収などについては以下の記事も参考にしていただければと思います。
BIMオペレーターに向いている人の特徴3選
将来性が高いBIMオペレーターですが、誰もが活躍できるわけではありません。ここでは、BIMオペレーターに向いている人の特徴を3つご紹介します。
地道な作業が苦にならない人
BIMモデルの作成は、一つひとつの部材をPC上で組み立てていく、非常に地道で根気のいる作業です。何時間もPCと向き合い、ミリ単位の精度で黙々と作業を続けることも少なくありません。
そのため、プラモデル作りやパズルが好きなど、細かい作業をコツコツと続けることが得意な人に向いています。華やかなイメージとは裏腹に、泥臭い作業が多いことを理解しておく必要があります。
学習意欲が高く新しいことが好きな人
先述の通り、BIMの世界は技術の進化が非常に速いです。新しいソフトやツールが次々と登場し、常に知識をアップデートし続ける必要があります。
そのため、「新しいことを学ぶのが好き」「自分のスキルを高めることに喜びを感じる」といった、高い学習意欲を持つ人でないと、続けるのは難しいかもしれません。
現状維持を好む人よりも、変化を楽しめるチャレンジャータイプの人が向いている仕事です。
コミュニケーション能力がある人
BIMオペレーターは、ただPCに向かって作業するだけではありません。設計者や現場監督など、様々な立場の人と関わりながら仕事を進めていきます。
相手の意図を正確に汲み取り、BIMモデルに反映させるためには、高いコミュニケーション能力が不可欠です。時には、専門家としてBIMの活用方法を提案したり、調整役を担ったりすることもあります。
人と話すのが好きで、チームで何かを成し遂げることにやりがいを感じる人に向いています。
年収アップを目指すためのキャリアプラン

BIMオペレーターとしてキャリアをスタートさせた後、どのように年収をアップさせていけば良いのでしょうか。ここでは、代表的な3つのキャリアプランをご紹介します。
BIMコンサルタントへのステップアップ
BIMオペレーターとして実務経験を積んだ後のキャリアとして、最も代表的なのがBIMコンサルタントです。BIMコンサルタントは、BIM導入を検討している企業に対して、導入支援や技術指導、ルール整備などを行う専門家です。
より上流工程からプロジェクトに関わることができ、年収も大幅にアップします。BIMオペレーターとしての現場経験は、コンサルタントとして活躍する上で大きな武器になるでしょう。
その他、BIMマネージャーやBIMコーディネーターという役割もあります。それらの仕事内容や必要なスキルについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
https://cadbim-3dcg.jp/4861.html
副業をしてみる
BIMスキルは、副業でも活かすことができます。例えば、クラウドソーシングサイトなどを利用して、個別のモデリング案件を受注したり、BIMの操作方法を教える講師をしたりといった働き方があります。
本業で得たスキルを活かして収入源を増やすことで、世帯年収を大きく上げることが可能です。まずは小さな案件からでも挑戦してみるのがおすすめです。
以下はCADオペの副業に関する記事ですが、そのままBIMオペにも適用できる内容になっておりますので、こちらの記事も参考にしてみてください。
https://cadbim-3dcg.jp/2347.html
フリーランスとして独立する
企業に属さず、フリーランスのBIMオペレーターとして独立するという選択肢もあります。自分のスキルと実績次第で、会社員時代よりも高い収入を得られる可能性があります。
働く時間や場所を自由に選べるのも大きな魅力です。ただし、自分で仕事を取ってくる営業力や、確定申告などの事務処理能力も必要になるため、相応の準備と覚悟が求められます。
フリーランスを目指す方は、独立前にこちらの記事を読んでおくと良いでしょう。
https://cadbim-3dcg.jp/2532.html
未経験からでも活躍するための学習ロードマップ
未経験からBIMオペレーターを目指すのであれば、計画的な学習が不可欠です。まずは、建築の基本的な知識を身につけ、その上でBIMソフトの操作を習得するのが効率的です。
独学で進める方法もありますが、モチベーションの維持が難しかったり、疑問点をすぐに解決できなかったりするため、専門のスクールに通うのがおすすめです。
スクールでは、体系的なカリキュラムで効率的に学べるだけでなく、就職サポートを受けられる場合もあります。
BIMの学習方法については、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。
https://cadbim-3dcg.jp/363.html
https://cadbim-3dcg.jp/615.html
条件の良い求人を見つけるための転職のコツ

せっかくBIMオペレーターになるなら、できるだけ条件の良い会社で働きたいですよね。優良企業を見つけるためには、転職エージェントの活用が非常に効果的です。
特に、建設業界に特化した転職エージェントは、一般には公開されていない好条件の非公開求人を多数保有しています。
キャリア相談にも乗ってくれるので、自分のスキルや経験に合った企業を紹介してもらえるでしょう。
複数のエージェントに登録し、多角的に情報を集めるのが成功の秘訣です。
転職活動を始める前に、以下の記事で優良な転職エージェントや求人の探し方について知識を深めておきましょう。
https://cadbim-3dcg.jp/2980.html
https://cadbim-3dcg.jp/674.html
https://cadbim-3dcg.jp/4832.html
【まとめ】BIMオペレーターはやめとけは本当か?後悔しないための選択
それでは、最後にこの記事のポイントをまとめます。
- 「やめとけ」と言われる理由: 給与、評価、学習の継続、未経験の壁、修正指示、残業、求人の質など、過渡期ならではの課題が存在する。
- それでもおすすめする理由: 国が推進するほどBIMの将来性は非常に高く、BIM人材の需要は今後も増え続けるため。
- 向いている人: 地道な作業が苦にならず、学習意欲とコミュニケーション能力が高い人。
- 成功への道筋: BIMコンサルタントやフリーランスなど明確なキャリアプランを描き、自分に合った学習方法と転職活動を行うことが重要。
「BIMオペレーターはやめとけ」という言葉は、この仕事の一部の側面だけを切り取ったものに過ぎません。確かに大変な面もありますが、それ以上に大きなやりがいと、明るい将来性が待っています。
大切なのは、ネガティブな情報に惑わされるのではなく、BIM業界の実態を正しく理解し、自分自身の適性を見極めた上で、後悔しない選択をすることです。この記事が、あなたのキャリア選択の一助となれば幸いです。
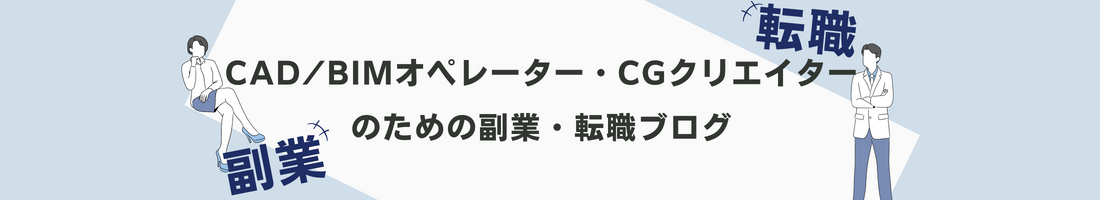
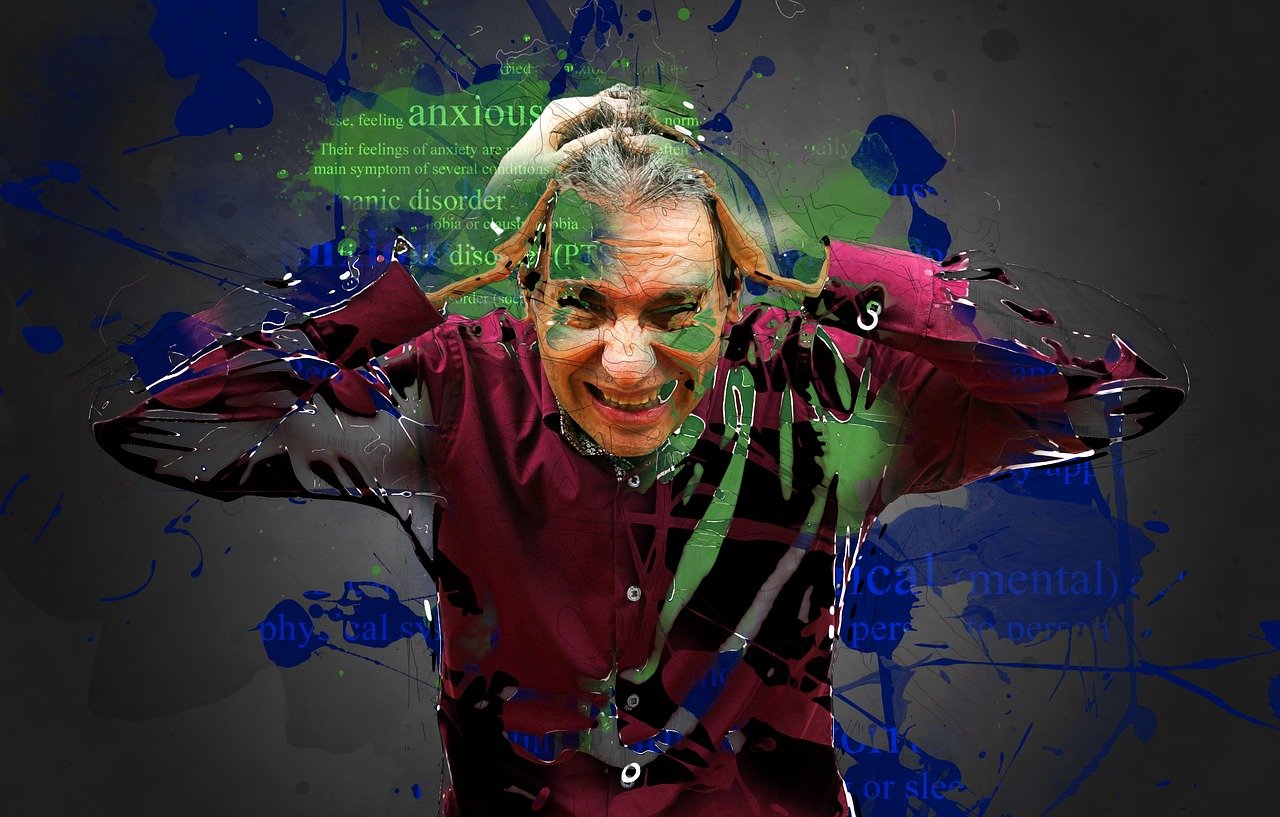





コメント