「3DCGのスキルを活かして、フリーランスとして自由に働きたい!」
「でも、実際のところ稼げるの?どうやって仕事を取ればいいんだろう…」
この記事にたどり着いたあなたは、3DCGフリーランスという働き方に興味や憧れを持ちつつも、具体的な道のりやリアルな実態が見えず、一歩を踏み出せずにいるのではないでしょうか。
まず結論からお伝えします。3DCGフリーランスは、計画的に正しい準備さえすれば十分目指せますし、会社員時代よりも大きく稼げる可能性を秘めた魅力的な働き方です。
なぜなら、3DCG業界はメタバースやVR/ARなどの新技術の発展に伴い、需要が急速に拡大している成長市場だからです。
確かなスキルと、自分を売り込むちょっとした営業のコツさえ掴めば、高単価な案件を獲得し、時間や場所に縛られずに働くことが可能になります。
何を隠そう、何をぶっちゃけよう、この記事を書いている僕自身が、独立した3DCGフリーランスです。会社員時代の年収は450万円ほどで、残業も多く「このままでいいのか…」と漠然とした不安を抱えていました。
独立当初は仕事の取り方もわからず、単価の安い案件で食いつなぐ苦しい時期もありました。しかし、ポートフォリオを戦略的に作り込み、エージェントやSNSをうまく活用することで、今では年収800万円を超え、時には海外からリモートで仕事をすることもできる生活を手に入れています。
もちろん、「フリーランスは不安定でしょ?」「営業なんてやったことないし、難しそう」「そもそも自分のスキルで通用するのか不安…」という声が聞こえてきそうです。
その気持ち、痛いほどわかります。確かに、会社員のような毎月の給与保証はなく、自分ですべてを管理しなければならない厳しさもあります。僕も最初は不安でいっぱいでした。
しかし、断言します。その不安は、正しい知識と具体的な行動計画があれば乗り越えられます。 むしろ、その先には会社員では得られなかったであろう大きなリターン(収入、時間、自由)が待っています。
この記事では、僕が3年間で経験した成功も失敗もすべて含めて、「3DCGフリーランスのリアルな実態」と「成功するための具体的なロードマップ」を、分かりやすく、正直にお伝えしていきます。
この記事を読み終える頃には、あなたの目の前の霧が晴れ、フリーランスへの道筋がハッキリと見えていれば幸いです。
3DCGフリーランスのリアルな実態|仕事内容・年収・将来性

まずは、多くの人が一番気になっているであろう「3DCGフリーランスって実際どんな感じなの?」という部分を、仕事内容からお金の話、将来性まで、僕の経験も交えながらリアルにお伝えしていきます。
3DCGフリーランスの主な仕事内容と案件の種類
一言で「3DCGの仕事」と言っても、その内容は多岐にわたります。フリーランスとして活動する場合、自分の得意分野を軸に、様々な案件に携わることになります。
主な仕事内容としては、以下のようなものが挙げられます。
- モデリング: キャラクター、背景、小物など、3DCGの「形」を作る仕事。最も基本的なスキルであり、案件数も多いです。
- テクスチャリング: モデリングされたオブジェクトに質感や色をつけ、リアルさを出す仕事。
- リギング: モデルに骨(ボーン)を入れ、動かせるように設定する仕事。
- アニメーション/モーション: キャラクターやオブジェクトに動きをつける仕事。
- エフェクト(VFX): 炎、水、爆発といった特殊効果を作成する仕事。
- ライティング/レンダリング: 制作した3DCG空間に光を当て、最終的な映像や画像を生成する仕事。
これらのそれぞれ必要なスキルは全然違いますが、私はモデラーをやっています。
モデラーは専用のソフトを使い3Dでモノの形状を組み立て、それにリアルな質感(アニメっぽい質感の場合もあり)を設定するまでを担当します。
観察力・造形力・デザイン力など多くのスキルが求められますが、3DCGにはなくてはならない存在です。
そして、これらのスキルがどんな業界で求められているかというと、本当に幅広いです。
- ゲーム業界: キャラクター、背景、アイテム、エフェクトなど、あらゆる3DCGアセットの制作。
- 映像・アニメ業界: 映画やアニメのCGパート、CM、MVなどの制作。
- 建築・不動産業界: 建築パース(完成予想図)や、VR内覧用のモデル制作。
- 製造業: 製品デザインのシミュレーションやプロモーション用CGの制作。
- VR/AR/メタバース業界: 仮想空間のアバターやワールドの制作。
フリーランスとしては、特定の工程(例えばモデリング)を専門に請け負うこともあれば、小規模なプロジェクトで複数の工程をまとめて担当することもあります。
自分のスキルセットや興味に合わせて、柔軟に仕事を選べるのが魅力ですね。
気になる収入事情!3DCGフリーランスの平均年収と単価相場
「で、結局いくら稼げるの?」という、一番大事な話をしましょう。これは僕も独立前に死ぬほど調べました(笑)。
会社員の3DCGデザイナーとの年収比較

まず、会社員とフリーランスの年収を比較してみましょう。
| 働き方 | 平均年収 | 特徴 |
| 会社員 | 400万円~600万円 | 安定した給与・福利厚生がある。スキルや経験年数に応じて昇給していくが、上限はある程度決まっている。 |
| フリーランス | 300万円~1,000万円以上 | スキル、営業力、実績次第で青天井。収入は不安定だが、高収入を目指せる。経費計上などの知識も必要。 |
厚生労働省の職業情報提供サイト「jobtag」によると、CG制作の平均年収は約484万円となっています。
一方、フリーランスはまさにピンキリ。僕の周りでも、独立したてで年収300万円台の人もいれば、特定の分野で圧倒的なスキルを持ち、年収1,500万円以上を稼ぐ猛者もいます。残念ながらフリーランスになるだけで会社員よりも断然稼げる!というわけではありません。
CG業界には使用期間としてまずは業務委託契約からスタート(成果を出せば契約社員・正社員へ登用)するケースもあるため、単価が低いお試しフリーランスも多くいます。
フリーランスは社員と違って契約を切りやすいので、まずは実力を見るためにお試しで契約するといったイメージです。
一方、一般的に会社員より多くのお金を稼ぐことが出来るのは“即戦力型”フリーランスです。
こちらはある程度仕事を一人こなせるだけのスキルや知識が必要になるため、すぐにそのレベルになるのは難しいですが、交渉次第ではがっつり稼ぐことも出来ます。
私のケースで言うと、最初に契約した映像会社の報酬はフリーランスながら大卒の初任給と同じくらいで、安定性の低い”お試し”フリーランスでした。
しかしその会社である程度スキルを身につけて次のゲーム会社と契約した時は、交渉によって前回の倍近い金額で契約することが出来ました。
これは当時社会人2年目だった私にとってはかなりいい条件だったともいます。
まとめますと、月当たりの収入は、1年目は23万、2年目は42万円(年収だと単純計算で500万ほど)でした。
このように報酬はクライアントと直接交渉して決める場合が多いので、ある意味自分の年収は自分で決められると言えます。
もちろんそこで高い報酬を提示するのであれば、それなりの実績とスキルなど交渉材料が必要になるでしょう。
また同じスキルをもった人でも、契約する会社の規模によって支払える金額も変わります。
たとえば大手ゲーム会社の大きなプロジェクトなどでは、開発費が膨大なため支払われる金額も多い傾向にあるようです。
スキル・実績で変動する案件単価の目安
フリーランスの収入は「単価×仕事量」で決まります。では、その「単価」はどれくらいなのでしょうか。これも案件の内容や求められるクオリティによって大きく変動しますが、僕の経験や周りのフリーランスから聞いた話をもとに、大まかな目安をまとめてみました。
【プロジェクト単位の報酬例】
| 案件内容 | 初心者~中級者レベル | 上級者・専門家レベル |
| キャラクターモデリング(1体) | 10万円~30万円 | 50万円~100万円以上 |
| 背景アセット制作(1点) | 5万円~15万円 | 20万円~50万円 |
| プロダクトモデル(1点) | 3万円~10万円 | 15万円~40万円 |
| 建築パース(1枚) | 8万円~20万円 | 30万円~70万円 |
【月額契約(業務委託)の報酬例】
- 実務経験1~3年レベル: 30万円~50万円/月
- 実務経験3年以上レベル: 50万円~80万円/月
- スペシャリストレベル: 80万円~120万円以上/月
あくまで目安ですが、スキルを磨き、実績を積むことで単価が上がっていくのがわかると思います。最初は単価が低くても、質の高い仕事をきっちりこなして信頼を勝ち取ることが、次の高単価案件に繋がっていきます。
3Dモデラーとしてフリーランスで働く場合の年収と仕事内容
3DCGの中でも特に「モデリング」を専門とする3Dモデラーは、フリーランスとして非常に需要の高い職種です。前述しましたが僕自身もモデリングを主軸に活動しています。
仕事内容は、キャラクター、背景、プロップ(小物)、メカ、建築物など、案件によって様々。求められる作風も、リアルなフォトリアル系からアニメ調のセルルックまで幅広く、自分の得意なスタイルを武器にすることができます。
年収は前述の通りスキルに大きく依存しますが、特に高い専門性が求められる分野、例えば「ハイエンドゲーム向けのリアルなキャラクター制作」や「精密な工業製品のモデリング」などができるモデラーは、高単価で取引される傾向にあります。
3Dモデラーの仕事内容やキャリアパスについて、より詳しく知りたい方は、こちらの記事も非常に参考にしてみて下さい。
3DCGフリーランスとして働くメリット・デメリット
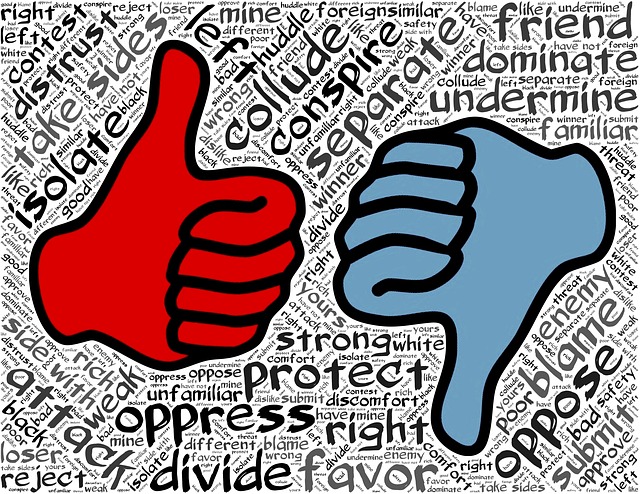
どんな働き方にも良い面と悪い面があります。独立してから僕が感じたメリットとデメリットを正直にお話しします。
メリット
収入の上限がない
スキルと営業力次第で会社員時代より大きく稼げる可能性があります。
スキルがあれば若いうちから活躍できる
何歳からでもフリーランスは目指せます。完全実力主義の業界なので、20代前半の若いうちから活躍し、稼いでいる方はたくさんいます。
自分の作ったものがダイレクトに評価され、次の仕事に繋がるので成長実感が得やすいです。
働く場所を選ばない
会社員だと基本出勤して会社で作業しますが、フリーランスだと自宅のPCで出来る案件も多くあります。
私も一時期、自宅で仕事をしていましたが、東京の満員電車に乗る必要もないですし、部屋でBGMをかけながら仕事をしていたのでかなりストレスが減りました。
九州の実家に帰って仕事をしていた時期もあります。
自由なワークスタイル
フリーランスだと、お金が欲しいからこの時期はがっつり働こうとか海外旅行に行きたいからこの時期は仕事入れないでおこうとかワークスタイルを自分で選択することが出来ます。
私の場合、契約期間が半年ほどの仕事が多かったのでその間しっかり働き、その後1か月間は何も仕事を入れず実家に帰ったり旅行に行ったりしてのんびりしていました。
海外旅行が好きだったり子供がいる人は特に向いていると思います。
仕事を選べる
自分のやりたい分野や、興味のあるプロジェクトに絞って仕事を受けられます。苦手な人間関係から解放されるのも大きなメリットです。
デメリット
収入が不安定
毎月決まった給料はありません。仕事が取れなければ収入はゼロです。常に営業活動や自己研鑽が必要です。
ソフトウェアが高い
3DCGに用いるソフトは高額なものが多いです。在宅で仕事を行う場合それらを経費として自分で購入しなければいけません。
例えばAutodesk Mayaのライセンス料で月30,000円ほどかかってました。
ただしクライアントの会社で作業する場合は、現場のPCに入っているソフトを使わせてもらえる場合がほとんどなのでこの心配はいらないでしょう。
自分で新技術を習得し続ける必要がある
私が考えるフリーランスの大きなデメリットはこれです。
フリーランスは基本的に即戦力として仕事を振られるので、成果を上げられない人はすぐに契約を切られます。
クライアントもフリーランスを教育する義務はないためどこが悪いかも教えてくれないことも多く、常に自分で調べて勉強し続けないとなかなか成長できません。
そのため私は以下のようなことで日々のスキルアップや、新しい技術を知り取り入れることをやっています。
- モデリングがうまい人のチュートリアル動画を見る
- 3Dモデルを購入してよく観察する
- 知り合いのCGモデラーに自分の作品を見せてフィードバックをもらう
フリーランスになる前には、しっかり勉強して一人である程度仕事をこなせるよう準備をしておくことをおすすめします。
自己管理能力が必須
納期管理、体調管理、お金の管理など、すべて自分で行う必要があります。サボろうと思えばいくらでもサボれてしまうので、強い意志が求められます。
孤独を感じやすい
基本的に一人での作業が多くなります。情報交換や相談できる相手がいないと、精神的に辛くなることも。
確定申告についてはそこまで大変ではなかった
確定申告についてはそこまで大変ではなかったので、すべて一人でやっていました。
というのもCGモデラーは経費としてお金がかかる項目は、ソフトのライセンス料や交通費、本などの資料など分かりやすく頻度も少なかったためです。
そのうえ今は便利な会計ソフトがあります。私は弥生を使っています。
会計ソフト利用がはじめてだったの不安でしたが、かんたんに使える作りになっていたので問題なく使えています。
私が選んだベーシックプランでは分からない操作が出てくると、電話・メール・チャット・画面共有などで丁寧に教えてくれたので非常に助かりました。
業務委託契約を結ぶ際の注意点とチェックリスト
フリーランスとして仕事をする際は、クライアントと「業務委託契約」を結びます。これが自分を守るための非常に重要な盾になります。口約束だけで仕事を進めるのは絶対にやめましょう。
契約書にサインする前に、最低でも以下の点は必ず確認してください。
【契約書チェックリスト】
- 業務範囲の明確化: 「何を」「どこまで」やるのかが具体的に書かれているか?(例:「キャラクターAのモデリングとテクスチャリングまで。リギングは含まない」など)
- 報酬額と支払条件: 報酬額は税込みか税抜きか?支払いはいつか?(月末締め翌月末払いなど)
- 納期と納品形式: 最終的な納期はいつか?どのようなデータ形式で納品するのか?
- 修正回数の上限: 無制限の修正ループを防ぐため、修正は「2回まで無料」など上限が定められているか?
- 著作権の帰属: 制作物の著作権は譲渡するのか、自分に残るのか?
- 秘密保持義務: どこまでの情報を秘密にしなければならないのか?
これらの内容が曖昧だと、後々「言った言わない」のトラブルに発展しかねません。もし契約内容で不安な点があれば、臆せずにクライアントに確認することが大切です。
近年、フリーランスを保護するための法律(フリーランス保護新法)も整備されつつあります。こういった国の制度についても知識として知っておくと、より安心して働けます。詳しくは、中小企業庁のウェブサイトなどで確認してみてください。
参考: フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン | 中小企業庁
3DCGフリーランスの将来性は?今後も稼げる?
結論から言うと、3DCGフリーランスの将来性は明るいです。
その理由は、やはりテクノロジーの進化にあります。
- メタバース・VR/AR市場の拡大: 仮想空間での活動が当たり前になれば、アバターやバーチャル空間そのものを作る3DCGクリエイターの需要は爆発的に増えます。
- 映像業界の進化: Netflixなどの動画配信サービスの普及により、高品質な映像コンテンツの需要が高まり続けています。実写では表現できない世界観をCGで作り出す機会はますます増えるでしょう。
- ゲーム業界の発展: よりリアルで没入感のあるゲーム体験を求める流れは止まりません。ハイクオリティな3DCGアセットは常に求められています。
- 非エンタメ分野への応用: 建築、医療、教育、製造など、これまでCGと縁が薄かった業界でも、シミュレーションやDX化のために3DCG技術の活用が進んでいます。
ただし、楽観視ばかりもしていられません。AIによる画像生成技術の進化など、クリエイターを取り巻く環境は常に変化しています。
今後もフリーランスとして稼ぎ続けるためには、新しい技術を積極的に学び、自分のスキルをアップデートし続ける姿勢が何よりも重要になります。
3DCGフリーランスになるための完全ロードマップ

さて、3DCGフリーランスのリアルな実態が見えてきたところで、ここからは「じゃあ、具体的にどうすればなれるの?」という、未経験から独立を目指すための完全ロードマップを解説していきます。
様々な3DCGソフトに触れておく
3DCGを制作するためのソフト(DCCツール)は数多く存在します。フリーランスとして活動するなら、特定のソフトを極めるのはもちろん大事ですが、複数のソフトに触れておくことを強くおすすめします。
なぜなら、プロジェクトによって使用されるメインツールが異なる場合があるからです。「Mayaしか使えません」という人より、「Mayaがメインですが、BlenderやZBrushでの作業も対応可能です」という人の方が、明らかに仕事の幅が広がりますよね。
- 業界標準ソフト: Maya, 3ds Max(映像、ゲーム業界で広く使われている)
- 近年需要が急増中: Blender(無料で高機能。スタートアップ企業や個人制作で人気)
- 特化型ソフト: ZBrush(スカルプトモデリングに特化), Substance 3D Painter(テクスチャ作成に特化)
まずは無料で始められるBlenderから学び始め、自分の進みたい業界が決まってきたら、そこで使われている主流ソフト(Mayaなど)を追加で学んでいくのが効率的な学習プランです。



【独学OK】フリーランスに必要なスキルとBlenderの重要性
「スクールに通わないとフリーランスにはなれない?」そんなことはありません。結論、独学でも3DCGフリーランスになることは十分可能です。僕も最初は独学からスタートしました。
ただし、そのためには技術スキルと、それと同じくらい重要な「ソフトスキル」を意識して身につける必要があります。
【技術スキル】
- 基礎的なCG制作スキル: モデリング、テクスチャリング、ライティング、レンダリングの一連の流れを理解し、実践できる力。
- 専門分野のスキル: 自分の武器となる得意分野(キャラクター、背景、メカなど)を深く追求する力。
- デッサン力・観察力: 立体的な構造を理解し、説得力のある形をアウトプットするための基礎画力。
【ソフトスキル】
- コミュニケーション能力: クライアントの要望を正確に汲み取り、円滑にやり取りする力。
- 自己管理能力: スケジュールやタスクを管理し、納期を守る力。
- 問題解決能力: エラーや予期せぬトラブルに直面した際に、自分で調べて解決する力。
- 営業・マーケティング能力: 自分を売り込み、仕事を獲得する力。
独学の最高の相棒となるのが、先ほども触れたBlenderです。無料で使える上に、ハイエンドな映像制作にも耐えうる非常にパワフルなソフトです。
YouTubeやUdemyなど、学習教材も豊富に揃っているため、独学でスキルを習得するには最適な環境が整っています。まずはBlenderで作品を一つ、最後まで作り上げてみることから始めましょう。
未経験者が最初にやるべきポートフォリオ作成術
フリーランスにとって、ポートフォリオは履歴書であり、名刺であり、最強の営業ツールです。未経験から仕事を取るためには、このポートフォリオの質がすべてを決めると言っても過言ではありません。
よくある間違いが、練習で作ったクオリティの低い作品をたくさん載せてしまうこと。これでは「この程度のものしか作れないんだな」と思われてしまいます。
ポートフォリオ作成で意識すべきは、「量より質」そして「戦略性」です。
- 目標設定: まず、自分がどんな業界(ゲーム、映像、建築など)で、どんな仕事(キャラクター、背景など)をしたいのかを明確にします。
- 作品制作: 目標に沿ったオリジナル作品を、最低3点、自分の持てる力のすべてを注ぎ込んで制作します。二次創作ではなく、オリジナル作品であることが重要です。
- クオリティアップ: 完成したと思っても、すぐに公開してはいけません。信頼できる人(SNSのクリエイターやコミュニティなど)に見てもらい、フィードバックをもらって徹底的にブラッシュアップしましょう。
- 見せ方の工夫: ポートフォリオサイト(ArtStationなどがおすすめ)に載せる際は、完成画像だけでなく、ワイヤーフレームやテクスチャマップなど、制作過程がわかる画像も一緒に載せると、技術力を効果的にアピールできます。また、「なぜこれを作ったのか(コンセプト)」「制作時間」「使用ツール」などを明記することも忘れないでください。
この「戦略的なポートフォリオ」があるだけで、未経験というハンデを覆し、企業の採用担当者の目に留まる可能性が格段に上がります。
3DCGフリーランスの具体的な案件の探し方・仕事の取り方
最高のポートフォリオが完成したら、いよいよ営業活動のスタートです。仕事の探し方は一つではありません。複数の方法を組み合わせることで、安定して案件を獲得できるようになります。
フリーランス向けエージェントの活用
僕が独立初期に最もお世話になったのが、フリーランス向けのエージェントです。
エージェントとは、自分のスキルや希望に合った案件を紹介してくれるサービスのこと。最大のメリットは、面倒な営業や契約交渉を代行してくれる点です。制作に集中したいクリエイターにとっては、非常に心強いパートナーとなります。
また、個人では見つけられないような企業の非公開案件や、高単価な案件を紹介してもらえるチャンスもあります。手数料(マージン)はかかりますが、それを上回るメリットがあると感じています。
3DCGに強いエージェントも数多く存在します。どこのエージェントが良いか迷った際は、こちらの記事で詳しく比較解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
クラウドソーシングサイトの賢い使い方
ランサーズやクラウドワークスといったクラウドソーシングサイトは、未経験者が「最初の実績」を作る場として非常に有効です。
ただし、注意点もあります。それは、全体的に単価が低い案件が多いこと。ここで消耗しすぎないことが重要です。
賢い使い方としては、
- まずは評価を貯めるために、簡単な案件を数件こなす。
- 高評価を得たら、少しずつ高単価な案件に応募していく。
- 長期的なお付き合いができそうなクライアントを見つける。
クラウドソーシングはあくまで「入口」と割り切り、実績と経験を積んだら、エージェントや直営業など、より単価の高いステージへ移行していくのがおすすめです。副業から始めるのも賢いやり方ですね。
SNSや交流会での直営業

ある程度の実績とポートフォリオが揃ってきたら、SNSを使ったセルフブランディングや、企業への直営業にも挑戦してみましょう。
X(旧Twitter)やArtStation、Behanceなどで継続的に作品を発信していると、それを見た企業担当者から直接仕事の依頼が舞い込んでくることがあります。
私もX(旧Twitter)にあげた作品がきっかけで仕事につながりました。
なので仕事は基本的にSNSで決まります。仕事募集中ですという投稿をすればクライアントから相談していただけたので。
フリーランスになるなら以下のようなSNSは絶対活用したほうがいいと思います。
また、業界のセミナーやクリエイターの交流会に顔を出し、名刺交換をして人脈を広げておくことも、思わぬ仕事に繋がることがあります。最初は勇気がいるかもしれませんが、これも立派な営業活動の一つです。
高単価案件を獲得し続ける3DCGフリーランスの特徴
フリーランスとして安定して、さらに高単価な案件を獲得し続ける人には、いくつかの共通点があります。
自分の強みを持つ
「なんでもできます!」というジェネラリストも良いですが、高単価を狙うなら「これなら誰にも負けない」という強み(専門性)を持つことが重要です。
例えば3DCGでロボットを作る仕事があったとして、ただクライアントから指示された通りに作業するだけの人は多くいます。
しかし自らデザインを考えてクライアントに提案し、オリジナリティのあるかっこいいロボットを作れるような人がいれば、その人の価値はぐんと上がるでしょう。
さらに、かっこいいロボットの仕事ならあの人に任せれば安心だな、とクライアントから直接指名されるようになれば条件交渉がかなり有利に進められます。
- 「リアルなクリーチャーのモデリングが得意」
- 「アニメ調の背景制作ならお任せください」
- 「建築パースのライティングには自信があります」
このように、自分の武器を明確にすることで、クライアントから「この仕事は、ぜひ〇〇さんにお願いしたい」と指名で依頼が来るようになります。そうなれば、価格競争から抜け出し、有利な条件で仕事を受けられるようになります。
高単価を狙うなら業界を選ぶのもコツ
高単価で言えばゲーム業界、特に大手がおすすめです。
開発期間も長いので一度契約が決まればしばらくは安定できます。
遊技機の映像も単価は高いですが、実績としてプロジェクトの名前を出せない場合が多いので注意が必要です。
その他の成長市場と言えば、例えば、建築業界のビジュアライゼーション(建築パース)や、医療分野での3DCGシミュレーションなどは、専門知識が必要とされるため、ゲームや映像業界よりも単価が高くなるケースもあります。
また、VR/ARやメタバース関連の案件も、まだ専門家が少ないため、先行者としてスキルを身につければ高単価を狙えるブルーオーシャンと言えるでしょう。
自分の興味と、市場の需要を照らし合わせながら、どの分野を主戦場にするか考えてみるのも面白いですよ。
更なる収益アップを狙いたい場合は、前述したようなフリーランスサイトでプロに相談するのも手です。
フリーランスの多くが働く土俵や収益化の論点が間違っているなどで収益アップにつながっていないケースも多いです。
まとめ:計画的な準備で成功する3DCGフリーランスを目指そう
最後に、この記事の要点をもう一度振り返ってみましょう。
- フリーランスの年収・単価はスキルと実績次第で青天井。会社員以上の収入も夢じゃない。
- 仕事はゲームや映像だけでなく、建築・医療など多岐にわたり、将来性も非常に高い。
- 独学でもフリーランスにはなれる。Blenderを相棒に、質の高いポートフォリオを作ることが最初の関門。
- エージェント、クラウドソーシング、SNSなどを組み合わせ、戦略的に案件を獲得していくことが成功のカギ。
3DCGフリーランスという道は、決して楽な道ではありません。常にスキルを磨き続け、自分で自分を律し、仕事を取りに行かなければならない、厳しくも刺激的な世界です。
しかし、その先には、時間や場所に縛られず、自分の好きなことで生きていくという、最高に自由な働き方が待っています。
この記事が、あなたの不安を少しでも解消し、フリーランスへの一歩を踏み出すためのコンパスとなれたなら、これ以上に嬉しいことはありません。
さあ、今日からあなたも、理想の働き方を実現するための準備を始めてみませんか?応援しています!
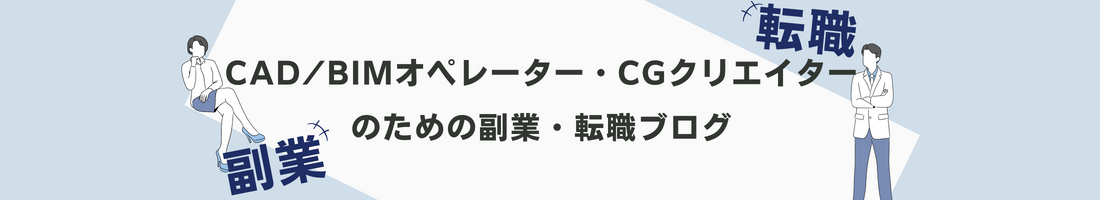


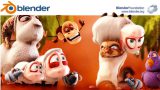





コメント